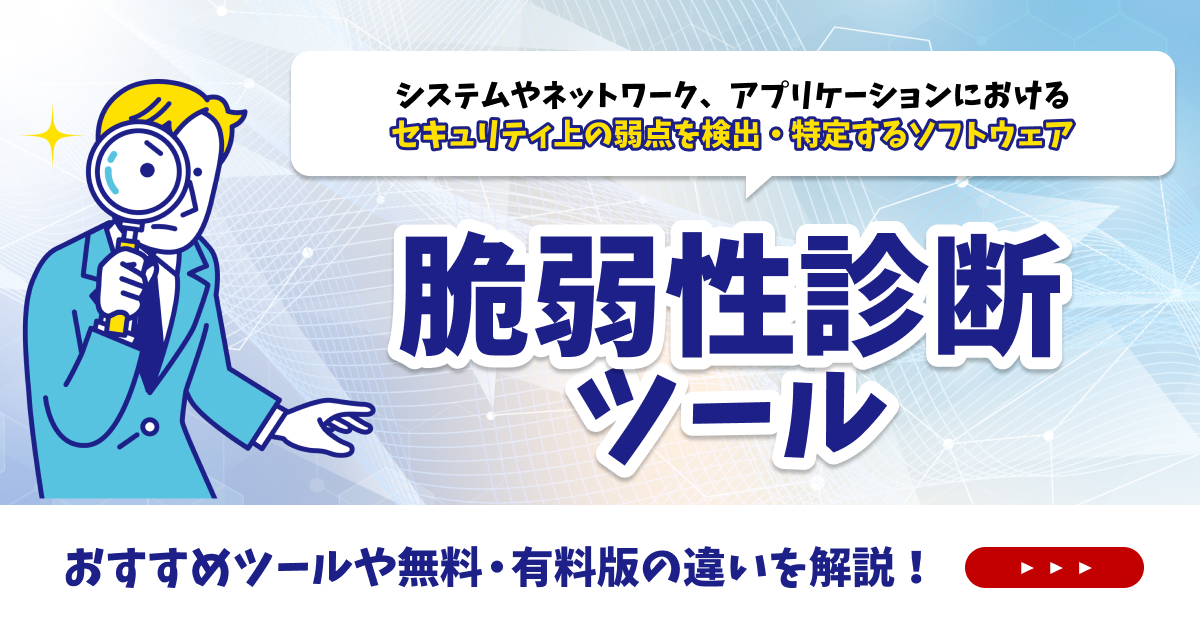近年、企業や個人を問わず、Webサイトやサーバー、クラウド環境などへのサイバー攻撃が急増しています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)でも、Webサイトやネットワークの脆弱性を早期に発見・修正することが、サイバー攻撃被害を防ぐ最も重要な対策の一つだとしています。
こうした脅威に対して有効なのが、システムの弱点を可視化できる「脆弱性診断ツール」です。ツールを使えば、Webアプリやネットワークの設定ミス、OSの更新漏れなど、攻撃の入り口となるリスクを自動的に発見できます。
この記事では、2026年時点でおすすめの脆弱性診断ツール15選を無料版・有料版に分けて比較紹介します。あわせて、ツールの仕組みや選び方、導入時の注意点もわかりやすく解説。 自社のセキュリティ対策を見直したい担当者や、どの診断ツールを選べばよいか迷っている方に役立つ内容です。
脆弱性診断ツールとはシステムの弱点を探す仕組み
脆弱性診断ツールとは、サーバーやWebアプリ、ネットワークなどに潜むセキュリティの弱点(脆弱性)を自動または手動で検出するためのツールです。攻撃者が悪用する可能性のある設定ミスや古いソフトウェア、認証の不備などをあらかじめ洗い出し、被害を未然に防ぐことを目的としています。
ツールは、サーバーやWebサイトに対して実際の攻撃を模倣する形でテストを行い、危険度や修正すべき箇所をレポート化します。これにより、専門的な知識がなくてもセキュリティリスクを把握しやすくなり、対策の優先順位づけも可能です。
従来はセキュリティ専門家が手作業で行っていた検査を自動化できるため、企業のセキュリティ運用コストを大幅に削減できるのも大きなメリットです。Webサービスやクラウド利用が一般化した今、脆弱性診断ツールは欠かせない存在となっています。
以下に脆弱性診断ツールが必要な理由やできること、タイプや特徴を解説します。
それぞれ見ていきましょう。
脆弱性診断ツールが必要な理由は抜け漏れを防ぐため
システムやWebサービスは、日々の更新や機能追加のたびに新しい脆弱性が生まれるリスクを抱えています。特に、OSやミドルウェア、Webアプリなど複数の要素で構成された環境では、すべてを人の手で確認するのは現実的ではありません。こうした見落としを防ぐために欠かせないのが脆弱性診断ツールです。
ツールを導入すれば、最新の攻撃手法や既知の脆弱性データベース(CVEなど)をもとに、定期的な自動スキャンが可能になります。これにより、発見が遅れることで生じる情報漏えいやサイト改ざんといった重大インシデントを未然に防ぐことができます。
また、脆弱性診断は社内だけでなく、取引先や顧客に対する「セキュリティ信頼性の証明」にもなります。セキュリティ要件を満たすために、取引条件として診断レポートの提出を求める企業も増えており、今や診断ツールはリスク対策だけでなく信用維持の手段としても重要な役割を担っています。
脆弱性診断ツールができることを具体的に解説
脆弱性診断ツールは、システムやWebアプリ、ネットワークの安全性を多角的に確認できる仕組みを備えています。単に「危険があるか」を調べるだけでなく、どの箇所が問題で、どのように修正すべきかまでをレポート化してくれる点が特徴です。
ここでは、代表的な3つの診断対象と主な機能を紹介します。
WebアプリやAPIの設定ミス・脆弱性を探す
脆弱性診断ツールの代表的な活用シーンが、WebアプリやAPIのセキュリティチェックです。これらはユーザーの入力や外部連携を通じて動作するため、わずかな設定ミスや入力値の処理不備が大きなリスクにつながります。たとえば、データベースを不正操作される「SQLインジェクション」や、悪意あるスクリプトを埋め込まれる「クロスサイトスクリプティング(XSS)」は、実際の被害事例が多い代表例です。
診断ツールはこうした脆弱性を模擬攻撃によって検出し、該当箇所やリスクレベルをレポート化します。開発者や運用担当者は、ツールの指摘をもとにソースコードや設定を修正し、再診断で安全性を検証できます。 Webサービスを運営する企業にとって、ツールの活用は“後付けの守り”ではなく“品質管理の一部”として欠かせない工程といえるでしょう。
OSやサーバーソフトの更新漏れを発見する
サーバーのOSやミドルウェア(Apache、Nginx、PHPなど)は、常に脆弱性が発見され、アップデートが繰り返されています。ところが、運用環境が複数に分かれていたり、担当者が限られていたりすると、更新作業が後回しになりがちです。その結果、既知の脆弱性を放置してしまい、攻撃者に狙われるリスクが高まります。
脆弱性診断ツールは、こうした更新漏れを自動で検出し、バージョン情報をもとに「どのソフトにどんな脆弱性があるか」を一覧で提示してくれます。特定のパッチが未適用の場合や、サポートが終了した古いソフトを使用している場合にも警告を出してくれるため、日常の点検業務を効率化できます。
とくにクラウドとオンプレミスが混在するハイブリッド環境では、すべてを人手で追跡するのは困難です。診断ツールを導入することで、運用チームが“重要な更新”に集中できる仕組みを整えられるのです。
ネットワークや通信の安全性を確認する
ネットワークの脆弱性は、外部からの侵入や情報漏えいにつながる重大なリスクです。特に近年は、VPNやリモートアクセス、クラウド接続など通信経路が複雑化しており、設定ミスや古い暗号化方式のまま運用されているケースも少なくありません。 脆弱性診断ツールは、外部からの不正アクセスを模したスキャンを実施し、開放ポートや不要な通信、暗号化設定の不備を洗い出します。
これにより「攻撃の入り口になり得る部分」を明確にでき、通信経路ごとに必要な防御策を立てやすくなります。 また、SSL/TLS設定やファイアウォールルールの確認、VPNの安全性チェックなど、ネットワーク診断に特化した項目を備えたツールも多く存在します。
リモートワークやクラウド利用が進む現代においては、ネットワーク全体の見える化と定期的な安全診断が不可欠です。ツールを活用することで、日常運用では気づきにくいリスクを早期に検出し、被害を未然に防ぐことができます。
脆弱性診断ツールの主なタイプと特徴
脆弱性診断ツールといっても、その仕組みや使い方はさまざまです。大きく分けると「自動診断ツール」「手動診断ツール」「クラウド型/オンプレミス型」の3タイプがあり、目的や運用体制によって最適な組み合わせが変わります。
自動診断ツールはソフトウェアが自動的にシステムをスキャンし、既知の脆弱性を短時間で検出できるタイプ。 一方、手動診断ツールはセキュリティ専門家が実際に操作して検証するため、複雑な攻撃パターンや業務特有のリスクまで深く分析できます。
さらに、導入形態も「クラウド型」と「オンプレミス型」に分かれ、クラウド型は手軽さと最新データの反映が強み、オンプレ型はカスタマイズ性とデータ保護の強さが魅力です。 ツール選びのポイントは、自社のセキュリティレベル・人材リソース・運用方針にどのタイプが最も合うかを見極めることにあります。
自動診断ツールはソフトウェアが自動でチェック
自動診断ツールは、専用のソフトウェアがシステムやWebサイトをスキャンし、既知の脆弱性や設定ミスを自動的に検出してくれるタイプです。手軽に導入でき、短時間で広範囲をチェックできるのが特徴です。特に、Webアプリやネットワーク、OS、サーバーなど、定期的な点検を必要とする環境でよく使われます。
代表的なツールには「AeyeScan」「Vuls」「Nessus」などがあり、企業だけでなく個人開発者にも利用されています。 自動化によって作業時間を大幅に短縮できる一方で、「誤検知」や「検出漏れ」が発生することもあり、最終的な判断には一定の知識が求められます。
セキュリティの第一歩としては非常に有効で、導入コストを抑えながら継続的にリスクをモニタリングできる点が大きなメリットです。
手動診断ツールはセキュリティ技術者が検証
手動診断ツールは、専門のセキュリティエンジニアが実際にシステムを操作し、攻撃を再現する形で脆弱性を調べる方式です。 自動診断では発見しづらい「ビジネスロジックの欠陥」や「意図しないアクセス経路」など、人の判断が必要な箇所を正確に見抜けるのが最大の強みです。
代表的な例としては「Burp Suite」「OWASP ZAP」などがあり、ツールを活用しながら人の知見を組み合わせることで、より実践的なセキュリティテストを行います。 その分コストは高く、作業時間もかかりますが、金融・公共・医療など高い安全性が求められる領域では不可欠な手法です。
重要なのは「自動と手動をどう組み合わせるか」。自社のリスクレベルに応じた最適な診断体制を整えることが重要です。
オンプレミス型とクラウド型の違いを解説
脆弱性診断ツールは「オンプレミス型」と「クラウド型」に分けられます。オンプレミス型は自社サーバーにインストールして利用する方式で、カスタマイズ性やデータ管理の自由度が高く、大企業や自治体などで採用されています。
一方、クラウド型はインターネット経由で利用するSaaSモデルで、導入が簡単で最新の脆弱性データを自動更新できるのが特徴です。 国産ツールでは「AeyeScan」や「Securify」「Shisho Cloud」などがクラウド対応を進めており、スキャン範囲やレポート機能も柔軟に設定可能です。
中小企業やスタートアップでは、コストと運用負担を抑えられるクラウド型が主流になりつつあります。逆に、厳密な機密保持や法的要件を重視する場合は、オンプレ型を選ぶケースも多いです。
脆弱性診断ツールの無料版・有料版の違いを解説
脆弱性診断ツールには、無料で使えるオープンソース型から、企業向けの有料クラウドサービスまで幅広い選択肢があります。 無料版は導入のハードルが低く、個人開発者や小規模サイトの安全確認に向いています。一方、有料版は診断範囲が広く、サポートやレポート機能も充実しており、企業全体でのセキュリティ対策に適しています。
どちらを選ぶかは、利用目的・リスクレベル・予算によって異なります。以下では、それぞれのメリットと注意点を整理します。
以下にそれぞれ解説します。
無料版のメリット・デメリット
無料の脆弱性診断ツールは、導入コストがかからず、すぐにスキャンを始められるのが最大のメリットです。 オープンソースの「OWASP ZAP」や「OpenVAS」「Vuls」などが代表例で、Webアプリやサーバーの初期診断を自分で試すのに適しています。 自動スキャンで主要な脆弱性を簡単に検出できるため、学習目的や自社テスト環境のチェックにも活用されています。
ただし、サポートや更新頻度はツールによって差があり、誤検知・検出漏れが発生することもあります。 また、レポート形式が専門的で読みにくい場合もあるため、結果の解釈には一定のITリテラシーが必要です。 無料版は「セキュリティ対策の入口」として有効ですが、継続的な運用や企業利用では限界があります。
有料版のメリット・デメリット
有料の脆弱性診断ツールは、無料版に比べて診断範囲・精度・レポート品質が格段に向上しています。 クラウド型の「AeyeScan」や「Securify」、海外製の「Qualys」「Nessus」などでは、最新の脆弱性情報を自動で反映し、検出内容に基づく優先度付け(リスクスコアリング)まで対応するものもあります。
また、導入支援や結果分析、再診断などのサポート体制が整っている点も大きな魅力です。 一方で、費用は月額数万円〜数十万円程度かかるケースが多く、コスト面で導入をためらう企業もあります。
自社のリスク許容度や運用リソースに合わせて、「無料ツールで自社検証 → 有料サービスで本格導入」という段階的な活用が現実的です。
脆弱性管理ツールの選び方は自社にフィットする選択を
脆弱性診断ツールを選ぶときに重要なのは、「有名だから」ではなく「自社の環境や体制に合っているか」です。 どんな範囲を診断したいのか、どの程度の精度を求めるのか、そして運用できる人材やコストのバランスをどう取るのか──これらを明確にすると、無駄のない選定ができます。
以下では、初心者から中小企業担当者までが押さえておくべき5つの比較ポイントを紹介します。
ぞれぞれ解説します。
Web・ネットワーク・クラウドなど自社の診断対象を確認
まず確認すべきは、「どの範囲を診断したいのか」という点です。WebアプリやECサイトを中心に運用しているなら、フォームやCookie設定などを検査できるWebアプリ診断タイプが適しています。 社内LANやVPNなど通信経路の安全性を確保したいなら、ネットワーク診断やサーバー診断に対応したツールが必要です。
また、AWSやAzureなどクラウドサービスを利用している場合は、クラウド構成の設定ミスや公開範囲を自動チェックできるSaaS型の脆弱性管理ツールを選ぶのが効果的です。 診断範囲を明確にすることで、余分なコストをかけずに本当に必要なツールを導入できます。
自社のセキュリティ体制や人材レベルとの相性を考慮
ツールの精度や機能が高くても、使いこなせなければ意味がありません。セキュリティ専任者がいる企業なら、詳細なスキャン設定やレポート分析ができる高度なツールも選択肢になります。 一方で、専門人材が少ない中小企業では、操作がシンプルで自動化機能が豊富なクラウド型ツールを選ぶと運用が続けやすくなります。
また、ツールによっては「検出結果を日本語でわかりやすく解説」「修正ガイド付きレポート」を提供しているものもあります。 自社の担当者がどこまで判断できるかを基準に、無理のないレベルのツールを選ぶことがポイントです。
検出精度・誤検知率・報告内容のわかりやすさを比較
脆弱性診断ツールを比較するうえで見落とされがちなのが、「精度と報告の質」です。検出漏れが多いとリスクを見逃す一方、誤検知が多すぎると修正作業に無駄な時間がかかります。 特にWebアプリ診断では、フォームや認証機構を誤ってスキャンすると、システムの挙動に影響が出る場合もあります。
有料ツールでは、検出結果に「リスクスコア」や「修正優先度」を付与してくれるものも多く、対応の順序づけに役立ちます。 レポート内容がグラフィカルで読みやすいか、経営層向けのサマリーが出せるかなど、運用後の使いやすさにも注目しましょう。
導入・運用コストを比較!相場は月額3万円前後から
脆弱性診断ツールの費用は、導入形態と診断範囲によって大きく異なります。クラウド型の自動診断ツールなら月額3万〜10万円前後が一般的で、都度スキャンや従量課金タイプもあります。 一方、オンプレミス型や手動診断を組み合わせる場合は、1回の診断で数十万円〜100万円を超えることもあります。
価格だけで判断するのではなく、「どのくらいの頻度で診断するのか」「誰が運用するのか」を踏まえて比較しましょう。 初期費用がかからず短期間で試せるクラウド型から始めるのも効果的です。
不測の事態に備えるためサポート体制を比較する
診断結果を受け取ったあとに、どう対応すべきか迷うケースは少なくありません。そのため、脆弱性診断ツールを選ぶ際は、レポート提出後のサポート体制も必ず確認しましょう。
国産ツールでは、メールやチャットでの質問対応、修正アドバイス、再診断の実施などをサポートするものが増えています。 海外製ツールを導入する場合は、サポート言語や時差の影響にも注意が必要です。
特に、セキュリティ担当が兼任の場合は「相談できる体制」があるかどうかが重要な判断材料になります。 導入後に孤立しないよう、運用を支援してくれるベンダーを選びましょう。
脆弱性診断ツールおすすめ15選を比較【無料・有料を比較】
診断結果を受け取ったあとに、どう対応すべきか迷うケースは少なくありません。 そのため、脆弱性診断ツールを選ぶ際は、レポート提出後のサポート体制も必ず確認しましょう。
国産ツールでは、メールやチャットでの質問対応、修正アドバイス、再診断の実施などをサポートするものが増えています。 海外製ツールを導入する場合は、サポート言語や時差の影響にも注意が必要です。
特に、セキュリティ担当が兼任の場合は「相談できる体制」があるかどうかが重要な判断材料になります。 導入後に孤立しないよう、運用を支援してくれるベンダーを選びましょう。
無料で使えるおすすめ脆弱性診断ツール4選
ここでは、初期費用をかけずに導入できる代表的な無料ツールを紹介します。オープンソースを中心に、Webアプリ・サーバー・ネットワークなど幅広い診断に対応しており、 個人利用や小規模サイトの基本的なセキュリティ確認に役立ちます。まずは無料ツールで診断の流れを体験したい人におすすめです。
それぞれ順に解説します。
OWASP ZAPはWebアプリ向けオープンソース定番
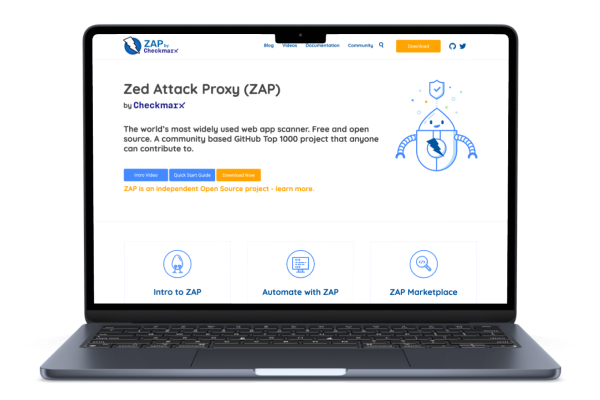
| 提供形態 | ソフトウェア型(オープンソース) |
|---|---|
| 対応範囲 | Webアプリケーション |
| 診断方法 | 自動診断+手動補助 |
| 料金目安 | 無料 |
| サポート体制 | コミュニティサポート(公式フォーラム・GitHub) |
| 開発主体 | OWASP Foundation(非営利団体) |
OWASP ZAP(Zed Attack Proxy)は、世界中のセキュリティ技術者が利用している無料の脆弱性診断ツールです。 オープンソースプロジェクト「OWASP」が開発しており、WebアプリやAPIの脆弱性を自動検出できます。 フォーム入力・Cookie・認証まわりの設定ミスなど、Web特有のセキュリティリスクを幅広くカバーし、ブラウザ連携で操作も直感的です。
また、プラグインを追加することでスキャン精度を高めたり、CI/CD環境に統合して自動診断を行うことも可能です。 個人開発から企業の検証環境まで幅広く使われており、「最初に触る脆弱性診断ツール」としてもおすすめです。
OpenVASはネットワークやサーバー全体を自動スキャン
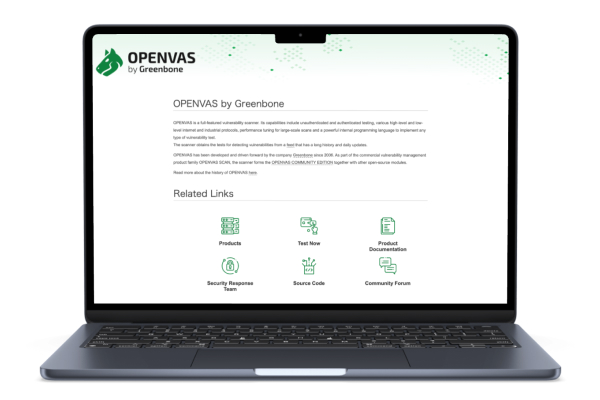
| 提供形態 | ソフトウェア型(オープンソース) |
|---|---|
| 対応範囲 | ネットワーク・サーバー |
| 診断方法 | 自動診断 |
| 料金目安 | 無料 |
| サポート体制 | コミュニティサポート(Greenbone Community) |
| 開発主体 | Greenbone Networks GmbH(ドイツ) |
OpenVAS(Open Vulnerability Assessment System)は、ネットワーク全体やサーバー環境を自動スキャンして脆弱性を検出するオープンソースツールです。 システム設定ミスや古いソフトウェアの存在、不要なポートの開放などを包括的にチェックし、ネットワーク層・OS層・サービス層を横断的に診断できます。
セキュリティ専門企業Greenbone Networksが開発を主導しており、商用版の「Greenbone Vulnerability Management(GVM)」と共通エンジンを使用。 定期的な脆弱性データベース更新にも対応しているため、無料ながら精度の高いスキャンを実現します。 社内LANやクラウド環境の基本的なセキュリティ状況を可視化したい中小企業にもおすすめです。
Vulsはサーバー・クラウド診断に強い国産オープンソース

| 提供形態 | ソフトウェア型(オープンソース) |
|---|---|
| 対応範囲 | サーバー・クラウド・コンテナ |
| 診断方法 | 自動診断(エージェントレススキャン) |
| 料金目安 | 無料 |
| サポート体制 | GitHub・ドキュメントによるコミュニティ支援 |
| 開発主体 | Future Corporation(日本/オープンソース開発) |
Vuls(バルス)は、サーバーやクラウド環境の脆弱性を自動検知できる国産のオープンソースツールです。 Linuxサーバーを中心に、パッケージ更新の遅れや設定ミスを検出し、CVE(共通脆弱性識別子)に基づいたリスク情報をわかりやすくレポートします。
特徴は「エージェントレス」で動作すること。対象サーバーに専用ソフトをインストールせず、SSH接続だけで診断が可能なため、運用負荷を抑えながら導入できます。 さらに、クラウド連携・スケジュールスキャン・メール通知などの機能も備えており、無料ながら企業利用にも十分対応できる完成度を誇ります。
NiktoはWebサーバー設定の脆弱性を高速チェック
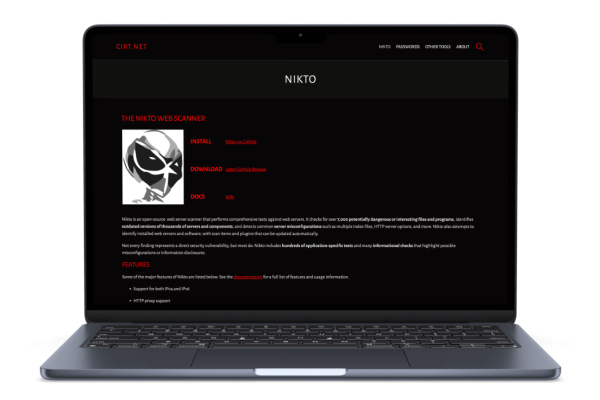
| 提供形態 | ソフトウェア型(オープンソース) |
|---|---|
| 対応範囲 | Webサーバー |
| 診断方法 | 自動診断 |
| 料金目安 | 無料 |
| サポート体制 | 開発者コミュニティによるサポート |
| 開発主体 | CIRT.net(米国) |
Nikto(ニクト)は、Webサーバーの設定ミスや古いバージョン、危険なスクリプトの存在を高速にスキャンできるオープンソースツールです。 軽量ながら約6万件以上の既知脆弱性データベースを参照し、短時間でサーバーのリスク状況を可視化できます。 Apache・Nginx・IISなど主要サーバーに対応しており、結果はテキストまたはHTML形式で出力可能です。
導入が容易で、単体利用はもちろん、他のセキュリティツールと組み合わせた診断の補助にも最適です。 企業の開発テスト環境や、個人のWebサイトを安全に運用したいユーザーにも向いています。 無料ながら「サーバーの健康診断ツール」として活躍する実用的な一手です。
LynisはLinux・Unix系のシステム監査にも対応
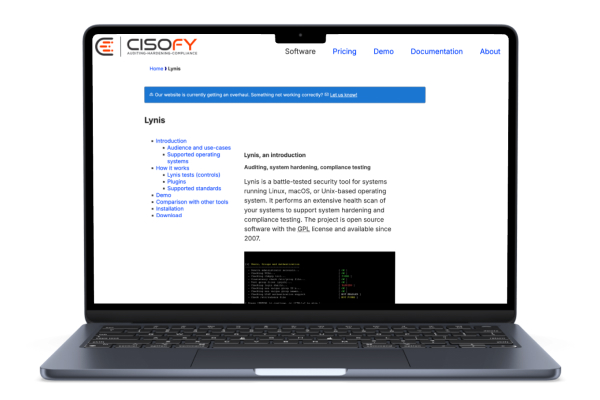
| 提供形態 | ソフトウェア型(オープンソース) |
|---|---|
| 対応範囲 | Linux・Unix・macOSシステム |
| 診断方法 | 自動診断(セキュリティ監査) |
| 料金目安 | 無料(有料エンタープライズ版あり) |
| サポート体制 | コミュニティ+商用サポート(CISOfy) |
| 開発主体 | CISOfy(オランダ) |
Lynis(リニス)は、LinuxやUnix系システムを対象にしたオープンソースのセキュリティ監査ツールです。 システム設定や権限管理、ログ監視、パッチ適用状況などを幅広く点検し、OSレベルのセキュリティを強化するのに役立ちます。 サーバー内部の設定ミスや不要なサービスの稼働も検出できるため、運用中の環境チェックにも最適です。
また、コマンドライン上で動作する軽量設計で、クラウドやコンテナ環境にも容易に導入可能。 結果はスコア形式で出力され、どの項目にリスクがあるかを直感的に把握できます。 企業サーバーやクラウド運用を行う管理者にとって、定期的なヘルスチェックツールとして非常に有用です。
有料で導入価値の高い脆弱性診断ツール11選
ここでは、企業や組織での導入実績が多く、信頼性や診断精度に優れた有料ツールを紹介します。自動診断に加えて、サポート体制やレポート品質など、運用面での安心感も重視したラインアップです。中小企業から大規模環境まで幅広く対応できる計11製品を比較します。
それぞれ順に解説します。
AeyeScanは国産クラウド型の自動診断ツール
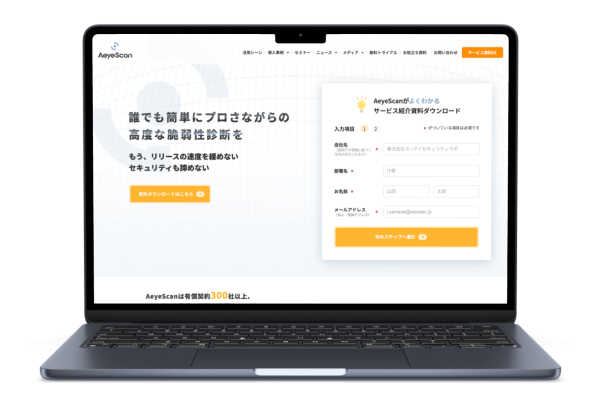
| 提供形態 | クラウド型(SaaS) |
|---|---|
| 対応範囲 | Webアプリケーション |
| 診断方法 | 自動診断+有人レビュー |
| 料金目安 | 要見積もり(無料トライアルあり) |
| サポート体制 | メール・オンラインサポート |
| 運営会社 | 株式会社エーアイセキュリティラボ |
AeyeScan(エーアイスキャン)は、株式会社エーアイセキュリティラボが提供する国産のクラウド型脆弱性診断ツールです。 AI技術を活用してWebアプリケーションの脆弱性を自動的に検出し、診断スピードと精度を両立しています。 クラウド上で動作するため、専用サーバーの構築やソフトのインストールが不要で、すぐに利用を開始できます。
主な特徴は、国産サービスならではの日本語UIと丁寧なレポート出力。 脆弱性の内容・リスク・対応方法をわかりやすく可視化でき、専門知識のない担当者でも改善方針を立てやすいのが魅力です。 中小企業から大手まで幅広く導入されており、国産クラウド型診断ツールとして高い信頼を得ています。
VexはWebアプリ診断に特化した国産ツール

| 提供形態 | オンプレミス/クラウド両対応 |
|---|---|
| 対応範囲 | Webアプリケーション・API診断 |
| 診断方法 | 自動診断+手動診断(ハイブリッド) |
| 料金目安 | 要見積もり |
| サポート体制 | 国内サポート・有人コンサルティング |
| 運営会社 | 株式会社ユービーセキュア |
Vex(ヴェックス)は、株式会社ユービーセキュアが開発したWebアプリケーションの脆弱性診断に特化した国産ツールです。自動診断と手動検証を組み合わせることで、高い精度と実用性を両立しています。
SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)などの主要脆弱性を網羅し、検出結果はレベル別に整理されるため、開発者や管理者が優先順位を付けやすい構成です。オンプレミスとクラウド両方に対応しており、セキュリティ診断のプロフェッショナルからも 信頼を集める代表的な日本製ソリューションといえます。
Securifyは資産可視化と診断を統合した国産ツール

| 提供形態 | クラウド型(SaaS) |
|---|---|
| 対応範囲 | IT資産全体・Web・クラウド |
| 診断方法 | 自動スキャン+分析レポート |
| 料金目安 | 月額制(要見積もり) |
| サポート体制 | 専任担当サポートあり |
| 運営会社 | 株式会社スリーシェイク |
Securify(セキュリファイ)は、株式会社スリーシェイクが提供するクラウド型の脆弱性管理プラットフォームです。企業ネットワークやクラウド資産を自動でスキャンし、構成情報と脆弱性情報を一元的に可視化します。
開発・運用・セキュリティの各チームが同じ画面でリスクを共有できる点が特徴で、発見から修正までの流れを効率化。AWSやGCPなどのクラウド環境にも対応しており、DevSecOpsの実践にも役立ちます。中堅〜大企業を中心に導入が進む国産の統合セキュリティツールです。
GMOサイバー攻撃ネットde診断は導入しやすい自動診断

| 提供形態 | クラウド型(SaaS) |
|---|---|
| 対応範囲 | Webサイト・サーバー・ネットワーク |
| 診断方法 | 自動診断 |
| 料金目安 | 月額40,000 円~ |
| サポート体制 | 日本語サポート・メール対応 |
| 運営会社 | GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社 |
GMOサイバー攻撃ネットde診断は、GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社が提供する自動脆弱性診断サービスです。WebサイトのURLを登録するだけで、クラウド上から自動的にスキャンを実行し、脆弱性の有無を短時間でレポート化します。
初期設定や専門知識が不要で、最短1営業日から診断が可能。中小企業や自治体にも導入しやすい料金体系が特徴です。診断後は専門エンジニアによる報告書解説や改善アドバイスも受けられるため、セキュリティ体制を強化したい企業に適しています。
Shisho Cloudはクラウド脆弱性管理を自動化

| 提供形態 | クラウド型(SaaS) |
|---|---|
| 対応範囲 | クラウドリソース(AWS/GCP/Azure) |
| 診断方法 | 自動スキャン+レポート生成 |
| 料金目安 | 月額制(無料トライアルあり) |
| サポート体制 | メール・チャットサポート |
| 運営会社 | GMOフラットセキュリティ株式会社 |
Shisho Cloud(シショウクラウド)は、GMOフラットセキュリティ株式会社が提供するクラウド環境向けの脆弱性管理プラットフォームです。AWSやGCP、Azureなど複数のクラウドサービスを横断的にスキャンし、設定ミスや不要な公開リソースを自動で検出します。
クラウド構成をコード化して監査する「Policy as Code」に対応しており、セキュリティポリシーを自動で適用・監視可能。インフラ担当者が手作業でチェックする手間を省き、運用の属人化を防ぎます。クラウド利用が進む企業にとって、持続的なセキュリティ管理を実現する国産SaaSです。
Nessusはネットワーク診断の世界的スタンダード

| 提供形態 | ソフトウェア型(クラウド版あり) |
|---|---|
| 対応範囲 | ネットワーク・サーバー・デバイス |
| 診断方法 | 自動診断 |
| 料金目安 | 月額$402.42〜 |
| サポート体制 | メール・ナレッジベース・英語サポート |
| 運営会社 | Tenable, Inc.(アメリカ) |
Nessus(ネサス)は、米国Tenable社が提供する世界的に定評のある脆弱性スキャナです。ネットワーク機器やサーバー、OS、ミドルウェアなど幅広い対象を自動でスキャンし、既知の脆弱性や設定不備を検出します。
豊富な脆弱性データベースと定期的なアップデートにより、最新の攻撃手法にも対応。オンプレミス・クラウド環境のどちらでも利用でき、セキュリティ担当者だけでなくIT運用部門でも導入しやすい構成になっています。無料版の「Nessus Essentials」も提供されており、学習・検証用途としても人気の高いツールです。
Burp SuiteはWebアプリ診断を効率化する定番ツール
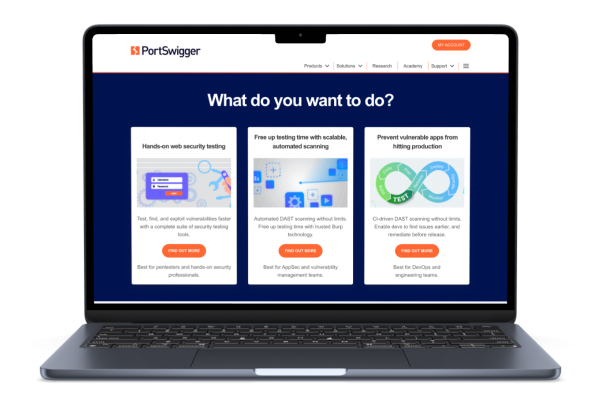
| 提供形態 | ソフトウェア型(Windows/Mac/Linux) |
|---|---|
| 対応範囲 | Webアプリケーション・API |
| 診断方法 | 手動+自動診断 |
| 料金目安 | 年額約449ドル〜(Pro版) |
| サポート体制 | ナレッジベース・フォーラム対応 |
| 運営会社 | PortSwigger Ltd.(イギリス) |
Burp Suite(バープスイート)は、イギリスのPortSwigger社が提供するWebアプリケーション脆弱性診断ツールです。プロキシ機能を利用して通信内容を分析し、不正なリクエストの送信や入力値検証などを通じて脆弱性を発見します。
自動スキャン機能を備えた「Professional版」と、手動診断に特化した「Community版」があり、用途に応じて選択可能です。SQLインジェクションやクロスサイトスクリプティング(XSS)など、主要な脆弱性検出に強みを持ち、セキュリティ技術者から世界的に支持されています。
Qualys VMDRは脆弱性検知と優先度管理を一元化
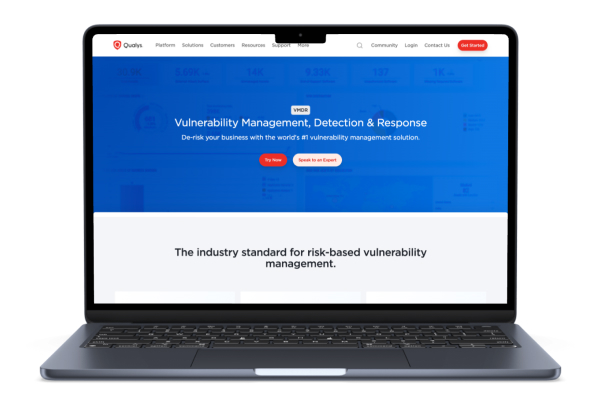
| 提供形態 | クラウド型(SaaS) |
|---|---|
| 対応範囲 | ネットワーク・エンドポイント・クラウド |
| 診断方法 | 自動スキャン+資産管理連携 |
| 料金目安 | 要見積もり(規模に応じて) |
| サポート体制 | 24時間グローバルサポート |
| 運営会社 | Qualys, Inc.(アメリカ) |
Qualys VMDR(Vulnerability Management, Detection and Response)は、米国Qualys社が提供するクラウド型の統合セキュリティプラットフォームです。ネットワーク、エンドポイント、クラウド、モバイルなど多様な資産をスキャンし、脆弱性の検知から修正までをワンストップで管理できます。
特に、AIを活用した「リスクベース優先度付け」機能により、攻撃される可能性の高い脆弱性を自動的に特定し、修正の優先順位を可視化。グローバル規模での可視化・管理が求められる企業に最適なソリューションです。自動レポートやAPI連携も充実しており、大企業や多拠点環境での導入実績が豊富です。
Rapid7 InsightVMはリスク可視化と分析に優れる

| 提供形態 | クラウド/オンプレ両対応 |
|---|---|
| 対応範囲 | ネットワーク・サーバー・クラウド |
| 診断方法 | 自動診断+ダッシュボード分析 |
| 料金目安 | 要見積もり |
| サポート体制 | オンライン・メールサポート |
| 運営会社 | Rapid7, Inc.(アメリカ) |
Rapid7 InsightVM(ラピッドセブン・インサイトVM)は、米国Rapid7社が提供する脆弱性管理ツールで、企業ネットワーク全体のリスクを可視化し、優先順位づけと修正支援を行うプラットフォームです。継続的なスキャンにより、システム・デバイス・アプリケーションの脆弱性をリアルタイムで把握できます。
ダッシュボードでのリスクスコア表示や、修正タスクを自動でチケット化する機能を備えており、IT部門とセキュリティ部門の連携を効率化。クラウド連携・API連携にも対応し、規模の大きな組織でも柔軟に導入できます。運用負荷を抑えながら、継続的なリスク管理を実現したい企業におすすめです。
Snykは開発段階で脆弱性を検知できる診断ツール

| 提供形態 | クラウド型(SaaS) |
|---|---|
| 対応範囲 | ソースコード・依存ライブラリ・コンテナ |
| 診断方法 | 自動診断(開発環境連携) |
| 料金目安 | 無料プランあり/有料は月額制 |
| サポート体制 | チャット・メール・開発者ドキュメント |
| 運営会社 | Snyk Ltd.(イギリス) |
Snyk(スニーク)は、開発者向けに設計されたクラウド型の脆弱性診断プラットフォームです。アプリケーションのソースコード、オープンソースライブラリ、コンテナ、インフラ設定(IaC)までを自動でスキャンし、開発段階で潜在的な脆弱性を検出します。
GitHubやGitLabなど主要な開発環境と連携でき、検出した脆弱性をリアルタイムで通知。修正方法の提案や自動パッチ適用にも対応しており、「セキュリティを開発プロセスに組み込む」DevSecOpsの実現を支援します。無料プランも用意されており、個人開発者から大規模チームまで幅広く活用されています。
脆弱性診断ツールを使うときの注意点と活用のコツ
脆弱性診断ツールは導入するだけで安全が確保されるものではありません。診断結果を正しく理解し、継続的に運用していくことが重要です。ここでは、ツールを活用する際に意識したいポイントと注意点を紹介します。
それぞれ順に解説します。
診断は一度きりではなく定期的なチェックが必要
脆弱性は日々新たに発見され、攻撃手法も進化しています。診断を一度実施して終わりにせず、定期的なスキャンを習慣化することが大切です。
一般的には、四半期ごとまたはシステム更新のたびに再診断を行うのが理想的です。特にクラウド環境やWebアプリを運用している企業では、継続的モニタリングを導入することでリスク低減につながります。
診断結果は放置せずに優先度をつけて改善を進める
診断ツールが提示する脆弱性の中には、緊急性が高いものと影響の小さいものが混在しています。重要度や影響範囲に応じて対応の優先順位をつけ、早急に修正を進めましょう。
特に「CVSSスコア」が高い項目や、外部から悪用されるリスクがある脆弱性は最優先で対処すべきです。レポートの活用により、社内の担当部門間での共有・対応もスムーズになります。
社内・外部の連携体制を整えて効率的に運用する
診断結果を活かすには、セキュリティ担当だけでなく、開発・インフラ・経営層が連携して改善に取り組む体制が重要です。
外部のセキュリティベンダーやコンサルタントを活用することで、専門的なアドバイスや修正支援を受けることも可能です。
自社のリソースや知識だけに頼らず、外部との協力体制を整えることで、運用効率と精度が大幅に向上します。
ペネトレーションテストとの違いを理解して使い分ける
脆弱性診断ツールは自動的にリスクを検出するのに対し、ペネトレーションテスト(侵入テスト)は人が実際の攻撃をシミュレーションして防御の強度を確認する手法です。
自動診断は広範囲のチェックに向いており、侵入テストは重要システムや本番環境での深掘り調査に適しています。両者を組み合わせることで、実効性の高いセキュリティ対策を構築できます。
脆弱性診断ツールに関するよくある質問に回答
最後に、脆弱性診断ツールを導入・運用する際によく寄せられる質問をまとめました。これからツールを選ぶ人や、すでに運用を始めている担当者の参考になる内容です。
どのくらいの頻度で脆弱性診断を行えばよい?
脆弱性診断は「一度実施すれば終わり」ではなく、継続的に行うことが基本です。
新しい脆弱性は毎日のように報告されるため、最低でも年に2〜4回の定期診断を推奨します。さらに、Webアプリの改修やシステム更新を行った際には、その都度スキャンを実施して安全性を確認しましょう。
特にクラウド環境やECサイトを運用している場合は、毎月や継続監視型の診断も検討すべきです。
無料ツールだけで十分なセキュリティ対策になる?
無料の脆弱性診断ツールでも基本的なチェックは可能ですが、検出精度やサポート範囲に限界があります。
小規模サイトや個人利用なら無料版でも問題ない場合がありますが、企業システムでは有料ツールや専門業者による診断を併用するのが現実的です。
有料版は誤検知率が低く、レポート機能やサポート体制も充実しているため、実務レベルでの運用に向いています。
診断結果のレポートはどんな形式で出力される?
ツールやサービスによって異なりますが、多くの場合はPDFやCSV形式のレポートが提供されます。
内容には、検出された脆弱性の詳細、影響度、修正推奨項目、対応優先度などが含まれます。中にはダッシュボード上で可視化し、管理者や開発チームと共有できるものもあります。
報告書は監査やISMS対応の証跡としても利用できるため、保管・共有の仕組みを整えておくと安心です。