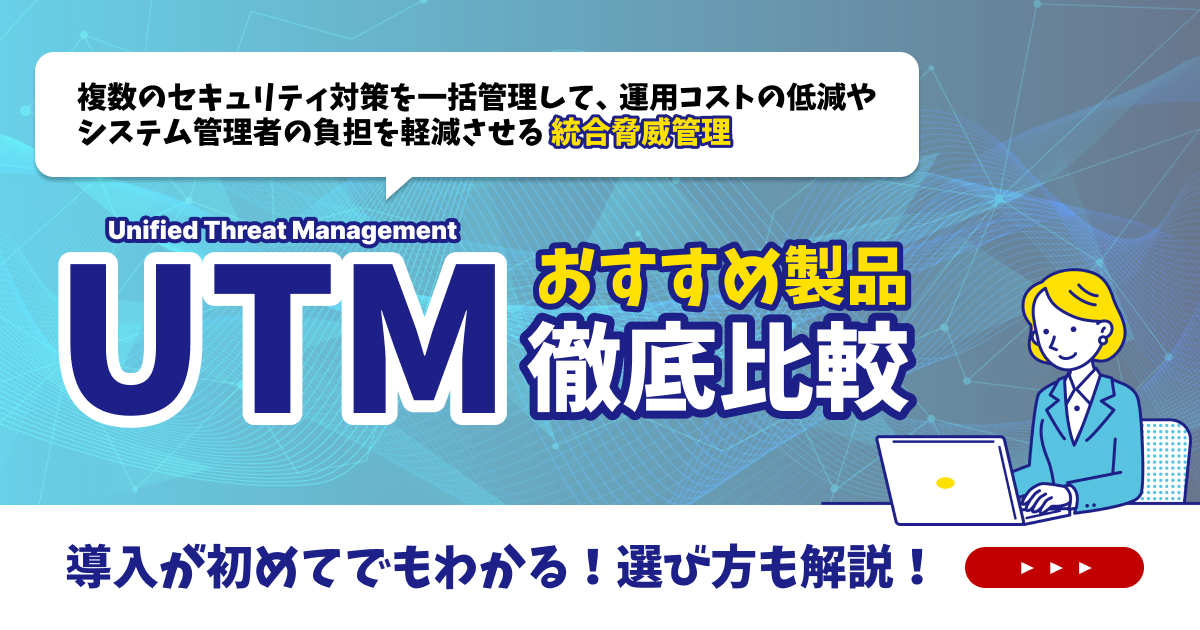サイバー攻撃の手口は年々高度化し、標的型メールやマルウェア感染、リモート環境への侵入など、あらゆる経路から企業ネットワークが狙われています。こうした脅威に対応するには、単一のウイルス対策ソフトだけでなく、ネットワーク全体を守る仕組みが必要です。
その代表的な対策が、UTM(Unified Threat Management:統合脅威管理)です。UTMは、ファイアウォールやIPS(侵入防止)、アンチウイルス、URLフィルタリングなど、複数のセキュリティ機能を一つの機器やクラウドサービスに統合し、効率的に運用できるのが特徴です。
経済産業省やIPA(情報処理推進機構)も、多層防御の重要性を示しており、UTMはその中核を担う存在といえます。
本記事では、UTMの仕組みや導入メリット、注意点、選び方のポイントをわかりやすく解説し、2025年最新のおすすめUTM製品13選をタイプ別に比較します。
UTMとは複数のセキュリティ機能を統合した総合防御システム
UTMとは、企業ネットワークを取り巻くさまざまな脅威に対し、複数のセキュリティ機能を一台でまとめて管理できるシステムを指します。これまでファイアウォール、ウイルス対策、迷惑メール対策などを個別に導入していた環境を、UTMで一元的に運用することで、設定や監視の手間を大幅に減らしながら防御力を高めることができます。特にセキュリティ専任者のいない企業や、拠点数が多い組織にとって、運用負担を軽減できる点が大きな魅力です。
UTMは、単なる「ウイルス対策装置」ではなく、外部からの侵入を防ぐと同時に、内部の通信を監視し、感染拡大を防止する包括的な防御システムです。サイバー攻撃の多くは複合的に行われるため、複数の防御レイヤーを組み合わせて対処できるUTMは、企業のセキュリティ対策における中核的存在といえるでしょう。
UTMの基本機能や導入タイプ、その他のセキュリティ機能との違いは以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
UTMの基本機能とその役割をわかりやすく解説
UTMには、代表的な4つの機能が備わっています。それぞれの役割を理解することで、どのように企業ネットワークを守っているのかが具体的に見えてきます。
ファイアウォール機能による不正アクセス防御
ファイアウォールは、外部からの不正な通信を遮断し、社内ネットワークを守る最前線の防御機能です。通信ポートやIPアドレス、プロトコルを監視し、不審なアクセスを自動的にブロックします。
UTMではこの基本機能を中心に、内部から外部への通信も制御できるよう強化されており、不正利用や情報漏えいの防止にも役立ちます。
IPS(侵入防止システム)による脅威の検知
IPSは、ファイアウォールをすり抜けた攻撃をリアルタイムに検知し、即座に遮断する仕組みです。
既知の脆弱性攻撃やゼロデイ攻撃(未修正の脆弱性を狙う攻撃)を検出できるため、未知の脅威にも柔軟に対応できます。UTMに組み込まれたIPSは、最新の脅威データベースと連携して自動更新される点が強みです。
URLフィルタリングで危険サイトへのアクセスを遮断
URLフィルタリングは、従業員がアクセスしようとするWebサイトを分類し、危険性の高いサイトを自動でブロックする機能です。
フィッシングサイトやマルウェア配布サイトへの誤アクセスを防ぐほか、業務効率を下げる娯楽サイトなどへのアクセス制御にも活用できます。UTMでは、カテゴリベースの設定やレポート機能が充実しており、ポリシー管理を簡単に行えます。
アンチウイルス機能によるマルウェア対策
アンチウイルス機能は、ネットワークを通過するファイルやメール添付データをスキャンし、ウイルスやランサムウェアを検知・削除する仕組みです。
従来の端末ごとのウイルス対策と異なり、UTMではネットワークの出入口で脅威をブロックするため、感染拡大を防ぐ一次防御として有効です。定義ファイルの自動更新やAI分析を採用する製品も増えています。
UTMの提供形態と導入タイプを理解して自社に合った運用を選ぶ
UTMは、一口に「導入する」といっても、その形態によって仕組みやコスト、運用負担が大きく異なります。大きく分けると、アプライアンス型・クラウド型・ゼロトラスト/SASE対応型・マネージド型の4種類があります。企業の規模やネットワーク構成、運用体制に合わせて最適なタイプを選ぶことが重要です。
アプライアンス型はオンプレミス環境に設置して運用
アプライアンス型UTMは、物理的な専用機器を社内ネットワークに設置して運用するタイプです。すべての通信を一度この装置に通すことで、外部からの攻撃やマルウェア感染、情報漏えいなどを一元的に防御します。オンプレミス運用のため、クラウドに依存せず社内ネットワーク内で完結できるのが大きな特徴です。
また、ファイアウォールやIPS、アンチウイルス、URLフィルタなどの複数機能をハードウェア上で統合的に動作させるため、通信処理の安定性や遅延の少なさにも優れています。特に、機密性の高い情報を扱う企業や、ネットワーク分離が求められる官公庁・製造業などでは依然として主流です。
一方で、機器の導入・保守・ライセンス更新が必要となるため、初期費用や運用コストはクラウド型に比べて高くなる傾向があります。とはいえ、拠点をまたぐ通信制御や帯域管理など、物理層での細かなチューニングが可能で、自社内で堅牢なセキュリティを構築したい企業にとっては最適な選択肢といえるでしょう。
クラウド型はSaaS形式で手軽に導入できるタイプ
クラウド型UTMは、物理機器を設置せず、インターネット経由でセキュリティ機能を利用できるサービス型の仕組みです。
導入までのスピードが早く、初期投資を抑えながら最新の防御機能を活用できます。ベンダー側で脅威データベースやソフトウェアの更新を自動的に行うため、常に最新状態を保てるのも強みです。
テレワークや外部接続が増えた企業では、クラウド上で通信を集約・監視することで、どこからでも安全なアクセスを確保できます。物理機器の保守負担がない反面、通信がクラウド経由になるため、ネットワーク構成によってはレイテンシ(遅延)が発生するケースもあります。しかし、柔軟性や拡張性に優れ、複数拠点・中小企業・スタートアップなどにとって導入しやすい形式といえるでしょう。
ゼロトラスト・SASE対応型は次世代のクラウドセキュリティ対策
ゼロトラストやSASE(Secure Access Service Edge)対応型UTMは、「信頼できる内部ネットワーク」という概念を捨て、すべての通信を検証する“境界なき防御”を実現します。VPN接続を使わず、ユーザー・端末・アプリケーション単位で動的にアクセス制御を行うのが特徴です。
この方式は、クラウドサービスやモバイル端末を多用する現代の企業環境に最適です。拠点や社員の所在地に関係なく、セキュリティポリシーを統一できるため、テレワーク・海外拠点・委託業者などを含む複雑なネットワークでも安全性を確保できます。
導入コストはやや高めですが、長期的には運用効率と可視化精度が高く、ゼロトラスト戦略を推進する企業にとって不可欠な選択肢といえます。
マネージド型は専門業者に運用を委託して負担を軽減
マネージド型UTMは、専門のセキュリティベンダーや通信事業者に運用・監視を委託する形態です。企業側は導入後、24時間体制での監視・アラート対応・アップデートなどを任せられるため、専任人材がいない中小企業でも高度なセキュリティ体制を維持できます。
SOC(Security Operation Center)による脅威分析やレポート提供を行うサービスも多く、異常検知から対処までを自動化できます。初期導入費用を抑えつつ、一定の月額料金で最新のセキュリティを維持できるのがメリットです。自社に専門知識がなくても、プロによる継続的なチューニングや運用改善を受けられるため、コストと安全性のバランスを重視する企業にとって非常に現実的な選択肢です。
UTMとファイアウォール・EDR・クラウドセキュリティとの違い
UTMは複数の防御機能を統合した「オールインワン型」の仕組みですが、ファイアウォールやEDR、クラウドセキュリティとは守る範囲が異なります。
ファイアウォールはネットワークの出入口を監視・制御する役割、EDRは端末内部の挙動を検知・分析する役割、クラウドセキュリティはクラウド上のデータやアクセスを保護する役割を持ちます。
UTMはこれらの要素を組み合わせてネットワーク全体を守る“統合防御基盤”であり、単一ツールよりも広範囲かつ効率的な防御を実現します。
UTMの必要性と導入するメリット
サイバー攻撃は年々巧妙化しており、ウイルスや不正アクセスだけでなく、標的型攻撃・ランサムウェア・内部情報漏えいなど、企業を狙う手口は多様化しています。
こうした中で、個別のセキュリティ製品を複数導入すると、管理が煩雑になり、設定の抜けや重複によってかえってリスクを生むケースも少なくありません。
その課題を解消する手段として注目されているのが、統合的に防御を行うUTM(統合脅威管理)です。ここでは、UTMを導入することで得られる主な4つのメリットを解説します。
それぞれ順に見ていきましょう。
複数の脅威対策を一元化し、管理の手間を削減
UTMの最大の利点は、ファイアウォール、IPS、アンチウイルス、Webフィルタリングなど複数のセキュリティ機能をひとつの管理画面で統合できる点にあります。これにより、担当者は複数ベンダーの設定や運用を個別に行う必要がなくなり、管理負荷を大幅に軽減できます。
また、UTMでは統合ログの取得・可視化が可能なため、社内の通信状況やセキュリティイベントをリアルタイムで把握しやすくなります。万一のインシデント発生時にも、原因の追跡や影響範囲の特定を迅速に行える点は、運用効率とセキュリティ精度の両立につながります。
外部攻撃から内部不正まで広範囲に対応
UTMは、外部からの侵入だけでなく、社内ネットワーク内で起こる不正通信や情報流出の兆候も検知します。たとえば、感染端末が外部サーバーと通信しようとする挙動を即座に検出し、遮断することが可能です。
さらに、業務端末のWebアクセスを制御したり、危険なファイルの送受信をブロックしたりすることで、従業員の不注意による情報漏えいリスクも減らせます。
つまりUTMは、外部攻撃防御と内部監視の双方をカバーし、社内外を問わずネットワーク全体のセキュリティレベルを底上げする仕組みといえるでしょう。
セキュリティ人材が不足していても導入しやすい
セキュリティ専門人材の確保が難しい中小・中堅企業にとって、UTMは運用負担を軽減できる実用的な選択肢です。UTMは設定画面が統一されており、アラート通知や定期レポート機能を備えることで、IT担当者が専門的な知識を持たなくても状況を把握しやすくなっています。
また、最近ではクラウド型やマネージド型のUTMも増えており、外部のセキュリティベンダーが運用・監視を代行してくれるサービスもあります。自社でSOC(セキュリティ運用センター)を持たなくても、高度な防御体制を維持できるのは大きな魅力です。
中小企業でもコストを抑えて導入できる
UTMは、従来のように複数の機器やソフトウェアを個別導入する必要がないため、コストパフォーマンスにも優れています。初期費用を抑えつつ、必要なセキュリティ機能をまとめて導入できることから、限られたIT予算でも堅牢なネットワーク防御を実現できます。
さらに、ライセンスやサブスクリプション形式で提供されるクラウド型UTMを選べば、月額課金で柔軟に利用可能です。トラフィックや従業員数の増減に応じてスケールアップ・ダウンができるため、成長段階の企業にも最適な仕組みといえるでしょう。
UTMのデメリットと導入前に注意すべき点
UTMは多機能で便利な反面、導入後の運用にあたってはいくつか注意すべきポイントがあります。セキュリティ機能をひとつに統合するという性質上、性能・運用・柔軟性のバランスを取ることが重要です。以下では、代表的な3つの注意点を挙げ、それぞれの課題をどう解消すべきかを解説します。
こちらもそれぞれ見ていきましょう。
機能を有効化すると通信速度が低下する場合がある
UTMは複数のセキュリティ機能を同時に稼働させるため、処理負荷が高くなりがちです。特にIPS(侵入防止)やウイルススキャン、Webフィルタリングをすべて有効化すると、トラフィック量の多い環境では通信速度の低下が発生することがあります。
この問題を防ぐには、導入前にスループット性能(処理能力)を確認することが大切です。メーカーが公表する数値を参考に、自社のユーザー数や通信量に見合ったスペックを選定しましょう。また、クラウド型UTMを採用すれば、スケーラブルに処理能力を拡張できるため、アクセス集中にも柔軟に対応できます。
専用製品に比べてカスタマイズ性は制限される
UTMは多機能を一括で提供する統合型システムであるため、特定機能を細かくチューニングしたい場合には制限を感じることがあります。たとえば、専用のファイアウォール製品やEDRのように詳細なルール設定や挙動分析を行う機能は限定的です。
このため、UTMは「すべてをカバーする万能ツール」ではなく、「基本的な防御を効率よく行う仕組み」として活用するのが現実的です。必要に応じて、重要システムには個別のセキュリティソリューションを組み合わせ、UTMをネットワーク全体の基盤として位置づける構成が理想です。
運用負荷やチューニングが必要な場合もある
UTMを導入した後は、初期設定だけでなく、運用中のルール最適化やログ分析など定期的なメンテナンスが求められます。特に、誤検知(false positive)や未対応の新種マルウェアが増えると、アラート対応や設定調整の工数が増えることがあります。
しかし、この課題も近年では大きく改善されています。マネージド型やクラウド型のUTMでは、ベンダー側が自動的に脅威データベースを更新し、チューニングを代行するサービスが一般的になっています。こうした仕組みを活用すれば、自社のリソースを最小限に抑えつつ、最新のセキュリティ状態を維持することが可能です。
UTMの選び方と比較ポイント7選
UTMは多機能である分、製品ごとの特徴や価格帯が大きく異なります。導入時には「何を守りたいのか」「どこまで自社で運用するのか」を明確にしたうえで、機能・性能・サポートの3要素を総合的に判断することが重要です。ここでは、導入前に確認しておきたい7つの比較ポイントを紹介します。
以下にそれぞれ解説します。
必要なセキュリティ機能をすべて備えているか確認
UTMは、ファイアウォール・IPS(侵入防止)・アンチウイルス・URLフィルタリング・スパム対策など、複数の防御機能を統合して提供します。製品によって標準搭載されている機能が異なるため、自社のリスクに合わせて「必須機能がそろっているか」を必ず確認しましょう。
特に、クラウド利用が多い企業は「SSL検査」や「アプリケーション制御」、ゼロトラスト対応を重視するとより安心です。
スループット性能と同時接続ユーザー数が十分か
UTMの性能を測るうえで最も重要なのが「スループット(処理能力)」と「同時接続ユーザー数」です。処理能力が不足すると、通信の遅延や業務システムのレスポンス低下につながります。
導入前には、社員数や通信トラフィックのピーク時を想定し、余裕を持ったスペックを選ぶことが大切です。拠点が多い企業では、VPN(拠点間接続)や負荷分散機能の有無もチェックしておくと安心です。
拡張性やライセンス更新のしやすさを比較
UTMは導入して終わりではなく、継続的な更新・運用が必要です。将来的にユーザー数や通信量が増える場合に、ライセンス追加やハードウェア拡張が柔軟に行えるかどうかを確認しましょう。
クラウド型UTMでは、契約プランのスケールアップ/ダウンが簡単に行えるものもあり、変化に対応しやすいのが特徴です。一方、アプライアンス型を導入する場合は、機器の保守・更新周期(3〜5年)も考慮しておくとよいでしょう。
クラウド対応やリモートワーク環境にも適応か
クラウドサービスやリモートワークが一般化した今、社内ネットワークだけを守る仕組みでは不十分です。クラウド型UTMやSASE対応UTMは、オフィス外からのアクセスも安全に制御できる点が強みです。
特に、Microsoft 365やGoogle Workspaceなどのクラウド利用が多い企業では、ID認証・ゼロトラストモデルと連携できるかどうかも比較のポイントになります。
管理画面の使いやすさと運用負荷の軽さを確認
UTMは運用担当者が日常的に扱うツールです。管理画面の見やすさやアラート通知の仕組みがわかりやすいかどうかは、長期的な運用効率を左右します。
近年はダッシュボードでトラフィックや検知状況を可視化できる製品が主流になっており、複数拠点の状況を一括で確認できるタイプが人気です。複雑な設定変更を頻繁に行う必要がないUI設計を選ぶことが、結果的に運用ミスの防止にもつながります。
価格相場は月額1万円〜数万円程度から利用できる
UTMの費用は導入形態によって大きく異なります。アプライアンス型では、本体価格が10万円〜100万円前後、さらに毎年のライセンス更新費・保守サポート費が発生します。一方、クラウド型UTMは初期費用がほとんど不要で、月額1万円〜数万円程度から利用できるケースが一般的です。
導入時は「初期コストの安さ」だけで判断せず、5年程度の総所有コストを基準に比較することが重要です。更新費や通信量の上限、追加オプション(VPN接続、ログ保管、サンドボックス分析など)を含めた見積もりを取り、運用フェーズまで想定しておくと無駄な支出を防げます。
特に中小企業では、クラウド型UTMやマネージドサービスを活用することで、機器購入・保守の手間を省きつつ、定額で高水準のセキュリティを維持できます。
サポート体制とアップデート頻度を重視して選ぶ
UTMは日々新しい脅威に対応するため、ベンダーのサポート体制とアップデート頻度が非常に重要です。日本語サポートや24時間対応の有無、障害発生時の復旧スピードなども比較ポイントになります。
特に中小企業の場合、導入後の設定変更やトラブル対応を外部に依存することが多いため、国内サポート拠点を持つメーカーを選ぶと安心です。脅威情報の更新が自動化されているか、定期レポートを提供してくれるかも、長期的な安心を左右する要素です。
UTM製品おすすめ13選を紹介!人気製品を比較
UTMには、オンプレミス型・クラウド型・ゼロトラスト/SASE対応型・マネージド型など、さまざまな導入タイプがあります。ここでは、代表的なアプライアンス型UTMから順に、国内外で高い評価を受ける主要製品を紹介します。機能や運用形態を比較しながら、自社の環境に最適な一台を検討してみましょう。
アプライアンス型UTM
社内ネットワークの分離が必要な製造業・官公庁・金融機関などでは今も主流であり、セキュリティ審査や監査対応にも適しています。各ベンダーが提供するアプライアンス型UTMは、性能や機能の方向性に個性があり、導入規模やネットワーク構成に応じた選定が重要です。
ここでは、世界的に導入実績が多く、国内でも高い信頼を得ている代表的な6製品を紹介します。
それぞれ順に解説します。
FortiGate
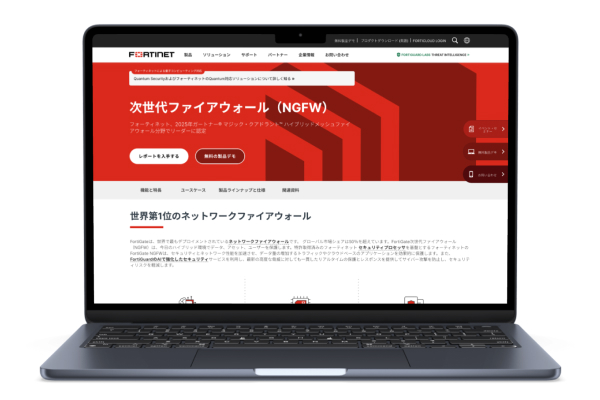
FortiGateは、世界トップクラスの導入実績を誇るFortinet社の代表的UTMシリーズです。ファイアウォール、IPS、アプリケーション制御、VPN、Webフィルタリング、アンチウイルスなど、多層的な防御機能を単一のハードウェアに統合し、高速かつ安定した通信処理を実現しています。
独自のセキュリティプロセッサ「FortiSPU」により、複数の機能を同時稼働させてもパフォーマンス低下を最小限に抑える設計が特徴。さらに、脅威情報共有プラットフォーム「FortiGuard Labs」との連携によって、世界中から収集された最新の攻撃情報をもとに自動更新が行われ、常に最新の防御状態を維持できます。
ラインナップは中小企業向けから大規模エンタープライズ向けまで幅広く、オンプレミス環境や複数拠点ネットワークにも柔軟に対応。安定性・拡張性・コストパフォーマンスの三拍子が揃った万能型UTMとして、多くの企業で標準的な選択肢とされています。
Palo Alto Networks PA Series

Palo Alto Networksの「PA Series」は、次世代ファイアウォール(NGFW)技術を先駆的に実装したUTM製品であり、世界中の政府機関・金融機関・大企業で採用されています。最大の特徴は、通信ポートやIPアドレスではなく「アプリケーション単位」で通信を可視化・制御できる「App-ID」技術にあります。これにより、従来のファイアウォールでは見逃していたクラウドアプリやシャドーITの利用も高精度に検知し、リスクを未然に防ぎます。
また、脅威情報基盤「WildFire」によるクラウド型サンドボックス分析を活用し、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃にも迅速に対応。AIによるリアルタイム検知と自動防御を組み合わせることで、EDRやXDRと同等レベルの脅威可視化を実現しています。
スループット性能は業界でも高水準で、拠点ネットワークからデータセンター、クラウド環境まで幅広く対応可能。ゼロトラストアーキテクチャを見据えた設計で、セキュリティ統合を進めたい企業に最適な製品です。
Check Point Quantum Spark

Check Point Quantum Sparkは、イスラエル発のセキュリティ専業ベンダー・Check Point社が提供する中小企業から大企業まで対応可能なUTMシリーズです。独自の「ThreatCloud」脅威インテリジェンス基盤により、世界中で発生する攻撃データを即時分析し、最新の防御パターンを自動更新。常に新しい脅威に対して先手を打てる体制を備えています。
ファイアウォールやIPS、アンチウイルス、アンチボット、URLフィルタなどを標準搭載し、機能ごとに細かくポリシー設定が可能。特に「SmartConsole」と呼ばれる管理画面は直感的で、IT専任者がいない企業でも運用しやすい設計が魅力です。
また、VPN機能による安全なリモート接続にも対応しており、拠点間通信やテレワーク環境にも強みを発揮します。アプライアンスは小型から高性能モデルまで幅広く、ライセンス体系も明瞭。限られた人員でも堅牢なセキュリティを維持したい中堅・中小企業に最適なUTMです。
Cisco Firepower

Cisco Firepowerは、ネットワーク機器で世界的シェアを誇るCisco Systemsが提供するUTM・次世代ファイアウォールシリーズです。長年のネットワーク技術の蓄積を活かし、ルーター・スイッチなどのCisco製品群との高い親和性を実現。ネットワークレベルからアプリケーション層までを包括的に可視化・制御できる点が最大の強みです。
高度な脅威防御機能「Cisco Talos」により、グローバル規模で収集された脅威インテリジェンスをもとにリアルタイムで攻撃を検知・防御。マルウェア分析、URLフィルタリング、IPS、VPNといった基本機能に加え、クラウド環境やリモートアクセスにも対応しています。
さらに、管理ツール「Firepower Management Center(FMC)」によって、全拠点のセキュリティポリシーやイベントを一元管理でき、運用負荷を大幅に軽減。既存ネットワークとの統合運用を重視する企業や、安定性・拡張性を求める大規模組織に特に適した製品です。
Sophos XGS Series

Sophos XGS Seriesは、イギリスのセキュリティ企業Sophosが提供する次世代UTM製品で、オンプレミスとクラウド双方の環境をシームレスに保護できる設計が特徴です。最大の強みは、同社のエンドポイント製品と連携する「Synchronized Security(同期型セキュリティ)」機能。ネットワーク上の脅威を検知すると、エンドポイント側の端末を即座に隔離するなど、自動連携によって被害の拡大を防ぎます。
独自の「Xstreamアーキテクチャ」により、SSL暗号化通信の高速スキャンやアプリケーション識別を実現し、従来課題だった遅延や誤検知を大幅に改善。IPS、アプリケーション制御、Webフィルタリング、VPNなどのUTM基本機能に加え、AIを活用した未知の脅威検知も強化されています。
クラウド型Sophos Centralから全拠点・全端末を一元管理でき、設定変更やレポート出力も容易。中堅・中小企業から大規模組織まで、拡張性と自動化を重視する企業におすすめの万能型UTMです。
SonicWall TZ Series
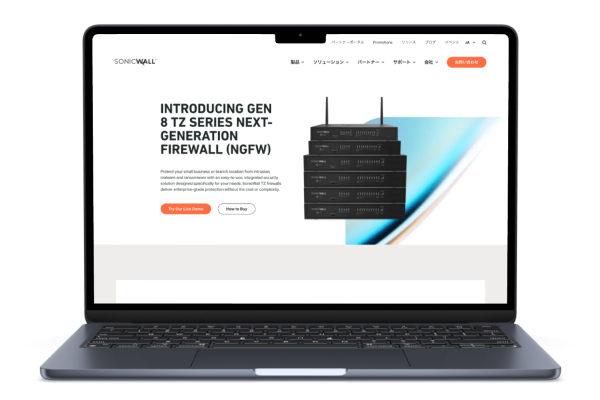
SonicWall TZ Seriesは、米国SonicWall社が提供する中小企業向けの次世代UTMシリーズで、コンパクトながらエンタープライズ級の防御性能を備えています。物理アプライアンスとしての安定性と、クラウド連携による柔軟な管理性を両立しており、導入コストを抑えつつ多層防御を実現できる点が評価されています。
ファイアウォール、IPS、アンチウイルス、コンテンツフィルタリングに加え、SonicWall独自の「Capture ATP(Advanced Threat Protection)」によるクラウド型サンドボックス分析を搭載。未知のマルウェアやランサムウェアもリアルタイムで検知・遮断します。また、「Zero-Touch Deployment」機能により、リモートでの初期設定・展開が可能なため、複数拠点を持つ企業にも最適です。
管理ポータル「Network Security Manager(NSM)」を通じてクラウド上で一元管理できるため、ゼロトラストやSASE戦略への移行を見据える企業にも適しています。堅牢性と運用効率を両立した、コストパフォーマンスの高いUTMです。
NEC UNIVERGE IXシリーズ

NEC UNIVERGE IXシリーズは、高速なVPN通信と安定稼働を重視した企業向けルーターであり、オプションライセンスによってUTM(統合脅威管理)機能を拡張できる点が特徴です。ファイアウォールやVPN、QoS制御を標準搭載しつつ、UTMライセンスを適用することで、IPS(不正侵入防止)、アンチウイルス、Webガード、URLフィルタリングといった多層防御を実現します。単なるアクセスルーターにとどまらず、セキュリティと通信制御を一台に統合できる柔軟な設計が強みです。
ラインナップはセンター用の「IX3000シリーズ」と拠点用の「IX2000シリーズ」で構成され、いずれも高速ブロードバンドや光回線、無線WANなど多様な通信方式に対応。UTM機能有効時でも最大約300 Mbpsの処理性能を確保し、クラウド利用やリモートアクセス環境でも快適な通信を維持します。さらに、クラウド管理サービス「NetMeister」やゼロタッチプロビジョニング(ZTP)機能を活用すれば、拠点ルーターの設置・設定・保守をリモートで一元管理可能です。
NEC製ならではの信頼性とサポート体制により、自治体・学校・医療機関など公共分野でも幅広く採用されています。ルーター性能とUTMセキュリティを両立した「拡張型UTM対応ルーター」として、ネットワークの安定運用と安全性を両立させたい企業に最適な選択肢といえるでしょう。
Yamaha UTXシリーズ
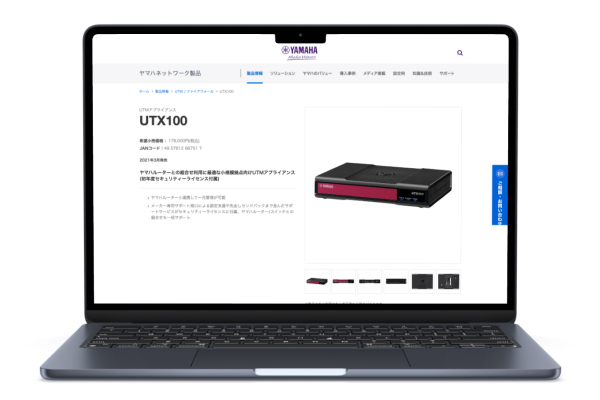
Yamaha UTXシリーズは、ルーター開発で培った通信制御技術をベースに、UTM(統合脅威管理)機能を搭載した法人向けネットワークセキュリティ機器です。ファイアウォールやVPN機能に加えて、アプリケーションコントロール、URLフィルタリング、侵入防止(IPS)、アンチウイルス、アンチボットといった多層防御を1台で実現。中小企業や拠点オフィスの通信を、シンプルな構成で安全に保護できます。
モデルは「UTX100」「UTX200」の2種類があり、拠点規模や通信速度に応じて選択可能です。Yamaha独自の管理ツール「YNO(Yamaha Network Organizer)」を利用すれば、複数拠点のUTX装置をクラウド上で一元管理でき、セキュリティポリシーの更新やファームウェアの適用も容易です。さらに、VPNルーター「RTXシリーズ」との連携にも対応しており、通信インフラとセキュリティ対策を統合的に運用できます。
シンプルなGUIと日本語マニュアルを備え、ネットワークの専門知識がない管理者でも扱いやすい設計が特徴です。導入から運用まで国産メーカーならではの手厚いサポートを受けられる点も信頼性が高く、国内の中小企業に高い評価を得ています。
クラウド型UTM
クラウド型UTMは、アプライアンス型と比べてメンテナンスの手間が大幅に少なく、最新の脅威情報やパターン更新も自動で行われます。特にセキュリティ専任者がいない企業にとっては、運用負荷の軽減とコストパフォーマンスの両立が可能な導入形態です。中小企業や複数拠点を持つ企業にも柔軟に対応できる点が評価されています。ここでは、クラウド型UTMの代表的な2製品を紹介します。
それぞれ順に解説します。
Trend Micro Cloud Edge

Trend Micro Cloud Edgeは、トレンドマイクロ社が提供するクラウド型のネットワークセキュリティサービスで、クラウド環境やリモートアクセスを中心に守ることを目的としています。ウイルスバスターシリーズで培われた脅威検知技術をベースに、ファイアウォール、IPS/IDS、URLフィルタリング、アプリケーション制御などの多層防御をクラウド経由で提供します。
最大の特徴は、クラウド上の集中管理コンソールによって、拠点や端末ごとの設定・監視を一括で行える点です。VPN接続も標準搭載されており、社外からのアクセス制御やゼロトラスト運用にも対応。新たなマルウェアやランサムウェアをAIで自動検出する仕組みも備えています。
初期投資が不要で、月額課金制によりコストを可視化できる点も魅力です。セキュリティ運用の専門知識を必要とせず、クラウド利用が進む中小企業・スタートアップにとって導入しやすいUTMソリューションです。
PFU iNetSec SF

PFUの「iNetSec SF」は、社内ネットワークに接続するあらゆるIT機器を検知し、不正な端末を自動で遮断する国産のセキュリティアプライアンスです。オンプレミス版とクラウド版が提供されており、クラウド版「iNetSec SF Cloud」では月額36,000円から利用可能。サーバー構築が不要で、短期間かつ低コストで導入できる点が特徴です。
クラウド経由で各拠点の端末を一元管理できるため、専用線を持たない小規模拠点やテレワーク環境にも対応します。社内のネットワーク構成を自動的に可視化し、私物PCやシャドーITデバイスなどの不正接続を即座に遮断。UTMやファイアウォールと連携することで、外部・内部の両面から多層防御を実現します。
製造業や医療機関など、IoT機器が多く管理が煩雑になりやすい環境で特に効果的です。クラウドを通じて最新の機器識別辞書や脅威データベースが自動更新されるため、セキュリティ担当者が不在の企業でも安心して運用できます。
ゼロトラスト・SASE型UTM
ゼロトラスト・SASE型UTMは、従来のファイアウォールやVPNに加えて、ゼロトラスト認証・アクセス制御・クラウド脅威防御を統合的に提供します。クラウド利用が多い企業や、SASE(Secure Access Service Edge)への移行を検討している企業にとって、セキュリティと利便性を両立できる選択肢です。
ここでは、ゼロトラスト対応を強化した代表的な製品を紹介します。
WatchGuard Firebox
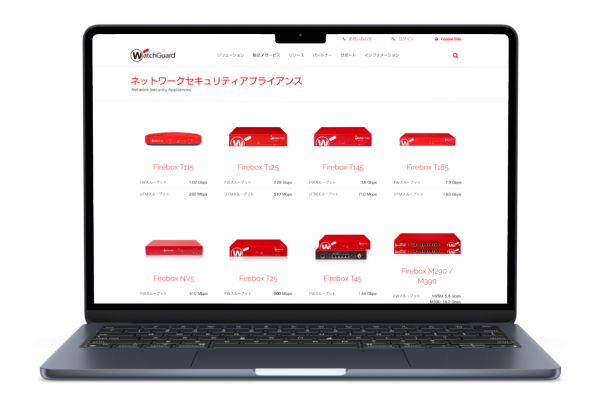
WatchGuard Fireboxは、米国WatchGuard Technologiesが提供するセキュリティアプライアンスで、ゼロトラストおよびSASE(Secure Access Service Edge)を見据えた統合型UTMとして高く評価されています。ファイアウォール、IPS、VPN、Webフィルタリング、マルウェア防御などの基本機能に加え、クラウド脅威検知「ThreatSync」やAI分析エンジンを搭載し、未知の脅威にも即応できる設計です。
管理プラットフォーム「WatchGuard Cloud」では、すべてのFireboxを一括管理でき、拠点追加や設定変更もクラウド経由で容易に実施可能。ゼロトラストに基づくユーザー認証・アクセス制御にも対応しており、従業員のデバイスや通信経路ごとにきめ細かいセキュリティポリシーを適用できます。
また、マルチテナント管理機能により、MSP(マネージドセキュリティプロバイダ)やIT管理部門による一元運用にも最適。クラウドとオンプレミスのハイブリッド環境を安全に統合したい企業におすすめの製品です。
マネージド型UTM
マネージド型UTMは、運用・監視・更新などを専門業者に委託できるサービス形態です。自社で機器を管理する手間がなく、セキュリティ担当者がいない企業でも安定した防御体制を維持できます。初期費用を抑えられる月額制プランも多く、導入ハードルが低いのも特徴です。ここでは、マネージド運用に強みを持つ代表的な2製品を紹介します。
それぞれ順に解説します。
おまかせサイバーみまもり

おまかせサイバーみまもりは、NTT東日本が提供する中小企業向けのマネージド型UTMサービスです。Fortinet製UTM機器をベースに、導入から監視・運用までをワンストップで提供するのが最大の特徴です。ユーザー企業はUTM機器を自社で管理する必要がなく、NTTのセキュリティセンターが24時間365日体制で脅威を監視し、異常時には迅速に通知・対応を行います。
通信の入口(インターネット接続)に設置することで、外部からの攻撃や不正アクセス、マルウェア通信などを自動的に遮断し、社内ネットワークの安全を確保します。また、専門知識が不要な管理ポータルから稼働状況を可視化できるため、セキュリティ担当者を置けない中小企業でも安心して導入できます。
さらに、定期的なレポートやファームウェア更新などもNTTが代行するため、常に最新の脅威情報に基づいた防御が可能です。初期費用を抑えた月額課金制で提供されており、IT予算が限られる企業にも導入しやすいマネージドUTMの代表格といえるでしょう。
IIJセキュアアクセスサービス
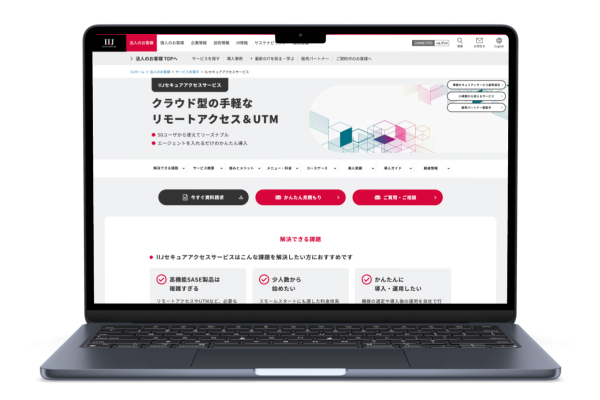
IIJセキュアアクセスサービスは、インターネットイニシアティブ(IIJ)が提供するクラウド型のマネージドUTMサービスです。従来のオンプレミスUTM機器を必要とせず、クラウド上でファイアウォール、IPS/IDS、アンチウイルス、URLフィルタリングなどの多層防御を実現します。IIJのネットワーク基盤にセキュリティ機能を統合しており、拠点間VPNやリモートワーク環境からのアクセスも安全に保護できるのが特長です。
IIJ SOC(セキュリティオペレーションセンター)による24時間365日の監視体制が整っており、異常検知時には迅速な通知と対処を実施。専任のセキュリティ人材がいない企業でも、高度な防御と運用をIIJに委託できます。また、クラウドベースであるため、拠点追加やユーザー数の増減にも柔軟に対応可能で、スケーラビリティにも優れています。
導入形態は月額制で、必要な機能を組み合わせて利用できるため、コスト最適化がしやすいのも魅力です。特に、全国に複数拠点を持つ企業や、ゼロトラスト移行を見据えたセキュリティ強化を進める中堅・中小企業に適したソリューションといえるでしょう。
UTMの導入に関するよくある質問に回答
UTMの導入を検討する際には、費用感や導入手順、運用体制など、さまざまな疑問が生じるものです。特に初めてセキュリティ対策を強化する企業では、導入後のサポート体制や他のツールとの違いを理解しておくことが重要です。
ここでは、UTMを導入する際に多く寄せられる質問をまとめ、検討段階で知っておきたい基本的なポイントをわかりやすく解説します。
UTMはもう古いと言われるのはなぜですか?
UTMが「古い」と言われる背景には、クラウド利用の増加やゼロトラスト・SASEといった新しいセキュリティ概念の普及があります。従来のUTMはオフィス内のネットワーク境界を守る仕組みであり、クラウドサービスやテレワーク環境では防御の範囲が限定されがちでした。そのため、「クラウドには対応しづらい」というイメージが残っています。
しかし近年は、FortiGateやSophosなど主要ベンダーが、クラウド連携・リモート接続・ゼロトラスト対応を強化した“次世代UTM”を提供しています。これにより、UTMは単なる境界防御装置から「統合セキュリティプラットフォーム」へと進化。クラウド型やハイブリッド運用を取り入れることで、今も多くの企業で主力の選択肢となっています。
UTMを導入すれば他のセキュリティ対策は不要ですか?
UTMを導入しても、すべてのセキュリティリスクを完全に防げるわけではありません。UTMは「ネットワークの入口・出口」を守る仕組みであり、内部端末のマルウェア感染や標的型攻撃の侵入後対応まではカバーしきれません。そのため、EDR(Endpoint Detection and Response)やメールセキュリティ、クラウドアクセス制御(CASB)などとの併用が推奨されます。
経済産業省やIPAも、企業のセキュリティ対策は「多層防御(Defense in Depth)」が基本としています。UTMはその中核を担う存在であり、他の製品・サービスと組み合わせることで、より強固な防御体制を構築できます。
中小企業が費用を抑えてUTMを導入するには?
中小企業がコストを抑えてUTMを導入するには、クラウド型やマネージド型UTMを選ぶのが効果的です。物理機器を設置する必要がないため初期費用が安く、専門人材がいなくても外部サービスが運用を代行してくれます。NTTやIIJなど通信キャリア系サービスでは、回線契約とセットでUTMを月額課金で利用できるプランも一般的です。
また、IPA(情報処理推進機構)が提供する「SECURITY ACTION」や「サイバーセキュリティお助け隊」などの支援制度を活用することで、導入費用や設定サポートの一部を補助してもらえる場合もあります。限られた予算でも、段階的にリスクを減らすアプローチを取ることが重要です。