サイバー攻撃は大企業だけでなく、中小企業や個人事業者も標的になる時代です。取引先や顧客情報が狙われるケースも多く、ウイルス対策ソフトだけでは十分に防げません。
こうした中で注目されているのが、端末上の不審な動きを検知し、被害を最小限に抑えるための仕組み「EDR(Endpoint Detection and Response)」です。
IPA(情報処理推進機構)も中小企業の情報セキュリティ対策ガイドラインを制定し、「中小企業もサイバー攻撃の被害対象となり得る」と警鐘を鳴らしています。また、経済産業省もサイバーセキュリティに関する注意喚起ページを公表し、「セキュリティ対策は自社や従業員だけでなく、取引先の信頼を守る第一歩」として、企業規模を問わず取り組む重要性を強調しています。
この記事では、EDRの基本的な仕組みや導入のメリット、選び方のポイント、そしておすすめのEDR製品12選をわかりやすく紹介します。これからセキュリティ体制を見直したい企業担当者の方にも役立つ内容です。
EDRとはエンドポイントを守る検知・対応型セキュリティ
「端末さえウイルス対策ソフトで守っていれば安心」という時代は終わりつつあります。
パソコンやスマートフォン、サーバーなど、従業員が業務で使うあらゆる機器は「エンドポイント」と呼ばれます。攻撃者はこのエンドポイントを入り口にして、社内ネットワークに侵入し、機密情報を盗み出したり、システムを停止させたりします。
近年では、ウイルス定義ファイルに頼る従来型のアンチウイルス(EPP)では検知しきれない「未知の攻撃」や「標的型攻撃」が増加しています。
そこで登場したのが EDR(Endpoint Detection and Response) です。EDRはエンドポイントで発生するすべての挙動を監視し、「検知」「分析」「対応」という3段階で不正な動きを特定し、被害を最小限に食い止める仕組みを提供します。
たとえば、見覚えのないプロセスが起動したり、通常では行わない通信が発生した場合、EDRはそれをリアルタイムで検知し、即座に管理者へ通知します。感染が確認された場合には、ネットワークから該当端末を自動で隔離することで、他の端末への拡散を防ぐことも可能です。
このように、EDRは「侵入されないように守る」のではなく、「侵入されても被害を最小限に抑える」ことを目的とした、次世代型のセキュリティ対策です。
EDRの基本的な機能やEPPとの違いは以下のとおりです。
それぞれ順に解説します。
EDRの主な機能は検知・分析・対応の3ステップ
EDRは大きく3つのステップで動作します。検知 → 分析 → 対応。このサイクルが素早く回ることで、攻撃者の動きを追跡し、被害を広げずに封じ込めることができます。
不審な挙動をリアルタイムに監視する機能
最初の段階は「検知」です。EDRは端末上で発生するログ(操作履歴や通信履歴など)を常時監視し、普段とは異なる挙動を検知します。
たとえば、未承認のアプリが起動したり、通常使わない夜間の時間帯にファイルへの大量アクセスが発生した場合、即座にアラートが上がります。これにより、攻撃の“兆候”を早期に捉えられるのが特徴です。
攻撃経路や影響範囲を可視化する分析機能
次のステップは「分析」です。EDRは検知した不審な動きを時系列で整理し、どの端末から侵入し、どの経路を通って拡散したのかを可視化します。これにより、原因究明や再発防止策の策定を迅速に行うことができます。
従来は専門家が時間をかけて調査していた内容も、EDRを使えば自動で可視化され、調査の効率が飛躍的に高まります。
感染端末の隔離・修復などの自動対応機能
最後のステップは「対応」です。EDRは攻撃を受けた端末をネットワークから自動的に切り離す「隔離」や、マルウェアを削除する「修復」を実行します。
さらに、攻撃発生時のログを保存し、再発防止のための証跡として活用できる点も重要です。管理者が遠隔で操作できる仕組みも整っており、複数拠点やテレワーク環境にも対応しています。
SOC・XDR・MDRとの連携でさらに強化できる仕組み
EDR単体でも高い効果を発揮しますが、さらに進化した仕組みである XDR(Extended Detection and Response) や、外部専門家による監視サービス MDR(Managed Detection and Response) と組み合わせることで、ネットワーク・クラウド・メールなど企業全体のセキュリティレベルを統合的に高めることが可能です。
特にSOC(Security Operation Center)との連携により、24時間365日の監視体制を実現し、人的リソースが限られる中小企業でも高度な防御を維持できます。
EPPとの違いは侵入前と侵入後の対策
EPP(Endpoint Protection Platform)は、主にウイルスやマルウェアを“侵入させない”ことに重点を置いた仕組みです。シグネチャ(既知のウイルス情報)をもとに、不正なプログラムを検知してブロックします。
一方のEDRは、“侵入された後にどう対応するか”にフォーカスしています。EPPでは見逃してしまう未知の攻撃やゼロデイ攻撃も、EDRが行動の異常から検知・分析・対処を行うことで補完します。
そのため、近年のセキュリティ対策では「EPP+EDR」を併用するケースが主流です。EPPが“予防接種”だとすれば、EDRは“発症後の迅速な治療”のような役割を担います。どちらか一方ではなく、両輪で運用することが安全性を最大化するポイントです。
EDRのメリットと効果は攻撃の早期発見と被害最小化
EDR(Endpoint Detection and Response)の最大の価値は、サイバー攻撃を「見逃さないこと」と「広げないこと」にあります。
従来のウイルス対策ソフトでは防ぎきれない未知の攻撃や標的型攻撃に対しても、EDRは不審な挙動を監視し、発生の瞬間からログを追跡。攻撃の“前兆”をつかむことで、被害を最小限に抑える仕組みを実現しています。
ここでは、EDRが企業にもたらす主な3つの効果を紹介します。
以下にそれぞれ解説します。
未知の攻撃にも対応できる高度な検知能力
EDRは、従来のように「ウイルス定義ファイルに載っている脅威」だけを対象とするのではなく、端末の挙動をリアルタイムに監視して異常を検知します。このため、まだ世の中で知られていないマルウェアやゼロデイ攻撃(修正プログラムが出ていない脆弱性を突く攻撃)にも対応できます。
たとえば、ファイルの暗号化を試みるプロセスや、外部サーバーへの不審な通信など、正常な業務では起こらない動きをEDRは瞬時に検知します。
この「行動ベースの監視」によって、未知の脅威や内部不正など、これまで防ぎきれなかったリスクにも強くなるのが大きな特徴です。
攻撃を受けても被害を最小限に抑える迅速な対応力
攻撃の検知後、EDRはそのまま「対応」フェーズへ移行します。感染した端末を自動的にネットワークから隔離したり、マルウェアの活動を強制停止させたりと、被害を広げないための即時対応が可能です。
さらに、EDRは攻撃の経路を可視化し、どのファイルが侵害され、どのユーザーが影響を受けたのかを素早く分析します。これにより、復旧作業にかかる時間を大幅に短縮し、業務停止や情報漏えいといった二次被害を防ぐことができます。
特に近年増えているランサムウェア攻撃では、こうした「即時隔離と可視化」が企業の被害額を左右する大きな要素となっています。
テレワークやクラウド環境でも安全性を確保
リモートワークやクラウド利用が進む中で、社員の端末が社内ネットワークの外にあることは当たり前になりました。しかし、こうした環境では、従来のファイアウォールやゲートウェイ型の防御だけでは十分に機能しません。
EDRは、社内外を問わず各端末に直接エージェントを配置し、どこからでも不審な挙動を監視できます。
つまり、社員が自宅や外出先で作業していても、セキュリティ監視が途切れることはありません。
また、クラウド上で管理するタイプのEDRなら、社内のセキュリティ担当者が複数拠点や全端末を一元的に管理することも可能です。
監査・法令対応・ガバナンス強化にも寄与
EDRの導入は、単に「攻撃を防ぐため」だけでなく、企業の信頼性を高めるための投資でもあります。EDRが記録する詳細なログは、情報漏えいや内部不正が発生した場合の調査証跡として活用でき、監査対応やコンプライアンスにも有効です。
また、経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」では、経営層が主体的にセキュリティを推進する姿勢が求められています。EDRのような検知・対応型システムを導入することは、まさにその実践の一歩といえます。
結果的に、顧客や取引先に対して「この企業はセキュリティを重視している」という信頼を示すことにもつながるのです。
EDRのデメリットと注意点や導入前の課題
EDRは非常に強力なセキュリティ対策ですが、導入すればすぐに安心というわけではありません。
その効果を十分に発揮するためには、コストや運用体制、社内リソースなど、いくつかの課題を理解しておく必要があります。ここでは、導入前に知っておくべき代表的なデメリットと注意点を紹介します。
以下にそれぞれ見ていきましょう。
導入・運用には初期費用や継続コストがかかる
EDRは高度な分析機能や管理システムを備えているため、導入時には一定の初期費用が発生します。
一般的には「1端末あたり月額1,000〜2,000円程度」が目安ですが、ベンダーや提供形態(クラウド型・オンプレミス型)によって価格差があります。また、導入後も定期的なライセンス更新やシステム維持のコストが発生します。
さらに、EDRは導入して終わりではなく、運用を継続するための人件費や監視体制の整備も必要です。「費用がかかるから導入しない」ではなく、「どの範囲で守るのか」「どの運用方式が最適か」を明確にすることが、コストを抑えながら効果を出す第一歩になります。
セキュリティに関する専門知識や人材が必要になる
EDRのログやアラートは、一般の業務担当者には理解が難しいことがあります。どの挙動が脅威で、どのアラートが誤検知なのかを判断するには、ある程度の知識と経験が必要です。そのため、EDRの導入後に「ツールはあるけれど運用できない」というケースも珍しくありません。
この課題を解決する方法として、マネージド型EDR(MDR)を活用する企業が増えています。MDRは、外部のセキュリティ専門チームが24時間監視や分析を代行するサービスで、自社のリソースが限られていても高度な防御体制を維持できます。特に中小企業やIT部門が少人数の組織では、現実的な選択肢のひとつです。
アラートの多さや運用負荷への対応策が必要となる
EDRは、異常を見逃さないように設計されているため、導入初期は大量のアラートが発生します。その中には「本当の脅威」と「誤検知」が混在しており、すべてを人力で確認するのは非効率です。アラートを放置すると本当に危険な攻撃を見逃すリスクがある一方で、対応をすべて人が行うのも現実的ではありません。
この課題に対しては、アラートのチューニング(しきい値の調整)や、自動対応ルールの設定が効果的です。さらに、XDR(拡張型検知・対応)を併用して、ネットワークやクラウド全体のログを統合管理することで、関連性の高いアラートをまとめて分析できるようになります。
こうした「運用負荷を軽減する工夫」が、EDRを長期的に活用する鍵となります。
中小企業が導入する際の現実的な対策
中小企業の場合、「費用」「人材」「運用負担」という三重の課題をすべて自社で解決するのは難しいのが実情です。しかし、だからといって対策を後回しにすれば、被害を受けた際の損失はさらに大きくなります。
現実的なステップとしては、まずはクラウド型のEDRサービスから検討するのがおすすめです。初期投資を抑えられるうえ、ベンダーがアップデートや監視体制を提供してくれるため、運用の手間も軽減できます。さらに、IPA(情報処理推進機構)や経済産業省が推進する「SECURITY ACTION」や「サイバーセキュリティお助け隊サービス」など、国の支援策を活用するのも有効です。
セキュリティ対策は「完璧を目指す」のではなく、「継続して改善していく」ことが重要です。自社の規模やリソースに合わせた形でEDRを導入し、少しずつ運用体制を整えていくことが、最も現実的で効果的なアプローチといえるでしょう。
EDRの選び方と比較ポイント7選を解説
EDR製品はベンダーによって機能や価格、運用形態が大きく異なります。そのため、単に「有名だから」「他社が使っているから」という理由で選ぶのではなく、自社の環境や目的に合った製品を選定することが欠かせません。
ここでは、導入を検討する際に比較すべき7つの視点を、わかりやすく整理します。
以下にそれぞれ解説します。
脅威の検知精度・対応スピード・可視化性能で選ぶ
EDRの基本性能を見極めるうえで最も重要なのが、検知の精度とスピードです。
どれだけ高度な脅威でも、検知が遅れれば被害は広がってしまいます。AIや機械学習を活用した高度な異常検知アルゴリズムを持つか、未知の攻撃(ゼロデイ攻撃やランサムウェア)に対応できるかを確認しましょう。
また、検知した後の「可視化」もポイントです。攻撃の流れを時系列で表示し、感染経路・影響範囲・侵入元をすぐに把握できる製品であれば、対応が格段にスムーズになります。特にセキュリティ担当者が少ない企業では、分析結果を直感的に理解できるダッシュボード機能があるかも大切です。
SIEM・XDRなど他セキュリティツールとの連携
EDR単体で完結する時代は終わり、他システムとの連携が重要になっています。
SIEM(Security Information and Event Management)と連携すれば、EDRのログをネットワークやクラウド、アプリケーションの情報と統合して一元分析できます。また、より広範な防御を実現するXDR(Extended Detection and Response)との統合は、近年のトレンドです。
EDRの検知結果をメール防御やクラウド監視と組み合わせることで、「全社的なセキュリティインテリジェンス」を構築できます。複数製品を使う予定がある場合は、API連携やクラウド統合の柔軟性も確認しておくと良いでしょう。
日常運用の負荷を減らす自動化機能の有無を確認
EDRの導入後、多くの企業が直面するのが「アラート対応の負担」です。検知力が高いほど通知も多くなり、すべてに人が対応していては手が回りません。そこで重要になるのが、自動化(オートメーション)機能です。
たとえば、疑わしいファイルを自動隔離する、特定の挙動を検知したら自動でスクリプトを実行するなど、一定のルールを設定できる製品を選ぶと運用効率が上がります。さらに、AIによるアラート分類や優先度付けが搭載されていれば、人的リソースの少ない組織でも現実的な運用が可能です。
「ツールを導入したが使いこなせない」という失敗を防ぐためにも、日常運用のしやすさを重視しましょう。
クラウド型かオンプレ型か運用環境に合う形態を選ぶ
EDRは提供形態によって、クラウド型とオンプレミス型の2種類に分かれます。
クラウド型は、インターネット経由で利用できるため初期導入が容易で、常に最新機能を利用できるのがメリットです。
一方、オンプレミス型は自社サーバー上で運用するため、データを社内に閉じた状態で管理でき、法規制や機密保持の厳しい業界に適しています。
たとえば、製造業や医療機関、金融業などでは「クラウド上にログを残せない」ケースも多く、オンプレ型を選ぶ企業が多い傾向にあります。逆に、IT企業やスタートアップのようにスピード重視の環境では、クラウド型の柔軟さが評価されています。
「自社の業務フローと法的制約の両面から判断する」ことが選定のコツです。
導入後の安心を左右するサポート体制・MDR対応を比較
EDRは導入して終わりではなく、「運用し続けること」が本番です。そのため、製品のサポート体制や運用支援サービスは必ずチェックすべき要素です。特に、24時間365日の監視体制や、日本語対応のヘルプデスク、アラートの分析支援があるかどうかは重要です。
また、自社内で十分な人材を確保できない場合は、MDR(Managed Detection and Response)対応製品を検討しましょう。MDRは、外部のセキュリティ専門チームがEDRの監視・分析・初期対応を代行してくれるサービスです。費用は上がりますが、「専門知識がない」「担当者が1人しかいない」といった企業でも安定した運用を実現できます。
端末単位や月額課金など料金体系の違いを比較
EDRの価格は、1端末あたり月額1,000円〜2,000円前後が一般的ですが、端末数・ログ保管期間・MDR有無・サポート範囲で大きく変動します。公開定価がないケースも多く、ベンダー見積りでの比較が前提です。初期費用の少ないクラウド/サブスク型から検討すると、全体コストを把握しやすくなります。
初期導入費が不要なサブスクリプション型もあれば、長期契約が前提のライセンス型もあります。また、クラウド型の場合は「アップデート費込み」かどうか、オンプレ型なら「保守費用」や「サーバー構築費」が別途発生することもあります。
単に月額料金だけを比較するのではなく、運用・保守を含めた総コストで比較することが大切です。「初期費用は安いが、運用コストが重い」ケースもあるため、3〜5年単位の費用感を想定して検討しましょう。
自社の業種・体制・セキュリティレベルに適した製品を選ぶ
最後に、EDRを選ぶうえで最も重要なのは「自社に合っているか」です。
同じEDRでも、使いやすさ・機能の深さ・管理画面の見やすさはベンダーによって大きく異なります。たとえば、製造業ではOT(制御系端末)に対応しているか、医療機関では個人情報保護法やISMS準拠ができるかなど、業界特有の要件を満たしていることが必要です。
また、担当者のスキルレベルも重要な判断軸です。専門知識を持つセキュリティ担当者がいる企業なら高度なカスタマイズ型EDRを、IT人材が少ない企業ならシンプルで直感的に操作できる製品を選ぶのが現実的です。
「高機能」よりも「無理なく運用できる」ことを優先するのが、長く使えるEDR選定のポイントです。
EDRの導入をおすすめする企業の特徴
EDRはすべての企業にとって有効なセキュリティ対策ですが、特に導入を強くおすすめできるのは「端末数が多い」「クラウド化が進んでいる」「専門人材が少ない」などの課題を抱える企業です。
ここでは、EDRの導入効果が高い5つの企業タイプを紹介します。
以下にそれぞれ解説します。
従業員が多く端末管理が複雑な企業
社員が多い企業ほど、ノートPCやスマートフォンなどのエンドポイントの数も増え、管理が難しくなります。たとえば、誰がどの端末を使っているか、どのアプリをインストールしているかを正確に把握するのは容易ではありません。こうした環境では、1台の端末が攻撃を受けると、社内全体に感染が拡大するリスクが高まります。
EDRは、各端末の挙動をリアルタイムで監視し、不審な動きを検知すると同時に自動的に隔離できます。
そのため、管理者がすべての端末を個別に監視しなくても、組織全体を統合的に守ることができます。
IT部門が少人数でも、EDRを導入することで“全社的なセキュリティガード”を常時稼働させることが可能です。
テレワークやクラウド活用が進んでいる企業
テレワークやクラウドサービスの利用が一般化した今、社外ネットワークからのアクセスが増え、従来の境界防御(ファイアウォール)だけでは対応できなくなっています。EDRは、社内・社外を問わず各端末の挙動を監視できるため、テレワーク環境にも最適です。
たとえば、自宅のWi-Fi経由で不審な通信が行われても、EDRが即座に検知し、攻撃の兆候を可視化します。さらに、クラウドストレージやSaaSアプリとの連携にも対応しており、クラウド上のファイル操作や通信履歴を追跡することも可能です。
従業員がどこで働いていても同じレベルのセキュリティを維持できるのが、EDRの大きな魅力です。
金融・医療・製造など重要情報を扱う業種
顧客情報・機密設計図・取引データなど、扱う情報の価値が高い業界は、攻撃者からの狙いも集中します。金融機関ではランサムウェア攻撃、医療機関では患者情報の漏えい、製造業では図面データの窃取などが深刻な被害を生んでいます。
こうした業種では、従来のウイルス対策だけでなく、侵入後の動きを検知して封じ込めるEDRの導入が事業継続の要になります。
特に「止められないシステム」を抱える製造ラインや病院などでは、異常発生時に自動で影響範囲を限定できるEDRが、被害拡大防止に直結します。
セキュリティ専門人材が不足している中小企業
多くの中小企業では、専任のセキュリティ担当者がいない、もしくは兼任で運用しているケースがほとんどです。そのような環境で複雑な攻撃に対応するのは困難ですが、EDRなら不審な挙動を自動で監視・記録し、外部ベンダーのサポートを受けながら対処できます。
さらに、MDR(Managed Detection and Response) 対応製品を選べば、専門家が24時間体制で監視と分析を行い、重大な脅威を代わりに検知してくれます。「人が足りないからできない」を解決できるのが、EDRの大きなメリットです。
すでにEPPを導入しているが不正侵入が不安な企業
多くの企業では、すでにウイルス対策ソフト(EPP)を導入しています。しかし、EPPは「侵入前の防御」が中心であり、侵入後の挙動監視や対応には弱点があります。最近の攻撃は、正規の通信を装ってEPPの検知をすり抜けるケースも少なくありません。
EPPとEDRを組み合わせることで、侵入を防ぎながらも、万が一侵入された場合に被害を最小限に抑えることが可能になります。
特に、ゼロトラストセキュリティの考え方が普及する中では、「防御+検知+対応」を一体化したEDRの導入が、企業リスクを大幅に下げる鍵となっています。
EDR製品おすすめ12選を紹介!人気製品を比較
ここでは、国内外で評価の高いEDR製品を12製品厳選し、それぞれの特長・導入メリット・向く企業のタイプなどを詳しく紹介します。数多く存在するEDR製品の中から「どれが自社に適しているか」を判断するための比較材料として活用してください。
各製品の「機能」「運用」「コスト」「サポート」といったポイントを理解すれば、単に知名度で選ぶことなく、自社の環境・業務・リスクレベルに適した選定が可能になります。
大企業・中小企業・テレワーク含む複数拠点・クラウド活用環境など、さまざまな運用タイプにおいて有効な選択肢を網羅していますので、導入検討時の参考にしてください。
それぞれ順に解説します。
Microsoft Defender for Endpoint

| 主な特徴 | AI/行動分析による検知と自動隔離、脅威ハンティング、Defender XDR連携 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型(Microsoft 365 Defender 基盤) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Android / iOS |
| 導入規模 | 中小企業〜大企業(グローバル展開にも対応) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(Microsoft 365 E5 Security 等のスイート、または単体ライセンス構成) |
| 連携機能 | Microsoft Sentinel(SIEM)、Intune(MDM/EMM)、Entra ID、Defender XDR、API連携 |
| サポート体制 | 日本語サポート、24/7(契約プランに準拠)、マネージド支援:Defender Experts for XDR |
| 無料トライアル | あり(期間・条件は時期により変動) |
| 提供企業 | Microsoft(マイクロソフト) |
Microsoft Defender for Endpointは、Microsoftが提供する法人向けの総合エンドポイントセキュリティソリューションです。
Windowsだけでなく、macOSやLinux、iOS、Androidにも対応しており、クラウドベースのAI分析により未知の脅威も検知できます。最大の特長は、Microsoft 365との高い親和性で、既存のOffice環境と統合することで、導入コストを抑えながらセキュリティを強化できる点です。管理コンソール上では攻撃経路を可視化でき、検知から隔離・修復までのプロセスを自動化。
すでにMicrosoft製品を利用している企業にとっては特に導入が容易で、クラウドとエンドポイントの一体的な防御を実現します。Windows環境を中心に運用している中堅・大企業に最適なEDRといえるでしょう。
CrowdStrike Falcon Insight XDR

| 主な特徴 | クラウドネイティブ構造による軽量EDR。脅威ハンティング、AI分析、自動修復対応。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型(Falcon Platform) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / モバイル(iOS・Android) |
| 導入規模 | 中堅企業〜大企業(グローバル展開・分散環境に強い) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(サブスクリプション:端末単位課金) |
| 連携機能 | XDR統合、SIEM連携、API接続(Splunk / ServiceNow / AWSなど) |
| サポート体制 | 24時間365日監視(Falcon OverWatch)、日本語サポートあり |
| 無料トライアル | あり(期間限定) |
| 提供企業 | CrowdStrike Holdings, Inc. |
CrowdStrike Falcon Insight XDRは、クラウドネイティブ構成とAIによる行動分析で高い評価を得ているEDRです。
端末だけでなく、クラウド・ネットワーク・アイデンティティを横断的に監視し、攻撃の全体像をリアルタイムで可視化します。軽量なエージェントを各端末に導入するだけで稼働でき、システムへの負荷が少ない点も魅力。自動隔離・修復機能を備え、発生から数秒で攻撃を食い止めることも可能です。
グローバル脅威インテリジェンスと連携しており、世界中の攻撃データを基に迅速な検知を実現。多拠点展開や海外拠点を持つ企業、または高度な攻撃を受けやすい業種に適しています。運用の高度化を目指す企業にとって、XDRの観点からもバランスの取れた選択肢です。
SentinelOne Singularity
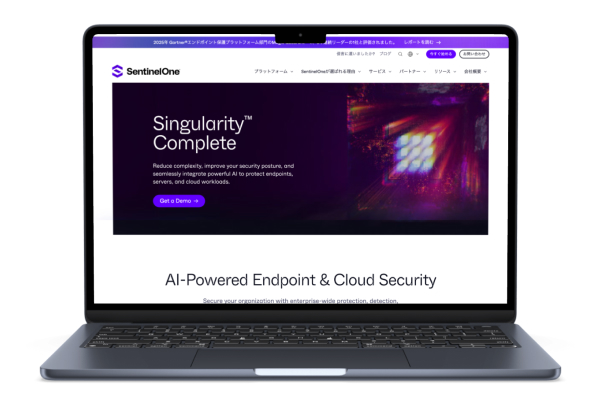
| 主な特徴 | AIによる自律防御と自動修復を実現。オフラインでも脅威検知可能。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型(Singularity Platform) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Kubernetes / 仮想環境対応 |
| 導入規模 | 中堅〜大企業(セキュリティ運用の自動化を重視する企業向け) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(ライセンスプラン:Core/Control/Completeなど) |
| 連携機能 | XDR対応、SIEM連携、API連携(Splunk / Slack / Oktaなど) |
| サポート体制 | 24/7サポート、日本語ドキュメントあり、MDRサービス「Vigilance Respond」提供 |
| 無料トライアル | あり(デモ・PoC環境提供) |
| 提供企業 | SentinelOne, Inc. |
SentinelOne Singularityは、AIによる自律型防御を実現した次世代EDRとして、世界的に高い評価を受けています。
端末上の軽量エージェントがリアルタイムに不審な挙動を監視し、攻撃を自動でブロック。さらに感染が発生しても「Rollback」機能によってシステムを自動復旧できる点が大きな特長です。これは、ランサムウェアによる暗号化被害を受けた場合でも、攻撃発生前の状態へロールバックできるという独自技術に基づいています。
また、クラウドベースの「Singularity Platform」によって、EDR・EPP・XDRを統合的に管理でき、SIEMやSOCとの連携も容易です。攻撃経路や影響範囲を可視化する「Storyline」機能により、調査工数を大幅に削減。自動化と可視化を両立させたい企業に適しています。セキュリティ専門人材が少なくても、設定後はAIが自動で最適化を行うため、運用負担を最小限に抑えられるのも魅力です。グローバル拠点を持つ企業やリモートワーク中心の環境にも適した万能型のEDRといえます。
Cybereason EDR
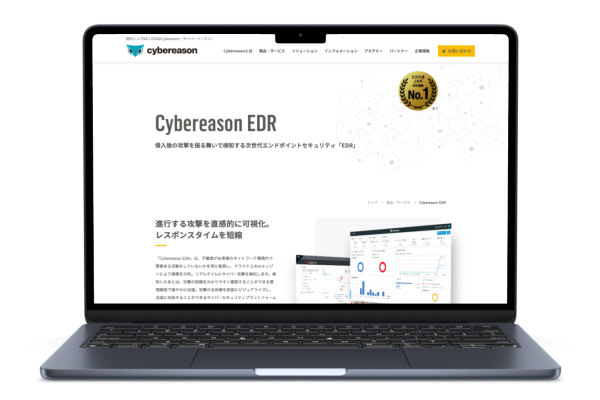
| 主な特徴 | 行動解析による攻撃の可視化と即応。侵入後の動きをグラフィカルに追跡。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型 / オンプレミス対応(ハイブリッド可) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux |
| 導入規模 | 中堅企業〜大企業(国内導入実績が豊富) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(端末数・オプションにより変動) |
| 連携機能 | SIEM連携(Splunk / QRadarなど)、SOAR統合、API連携可 |
| サポート体制 | 日本語サポート、24時間監視オプション、MDRサービス「Cybereason MDR」提供 |
| 無料トライアル | あり(デモ・PoC対応) |
| 提供企業 | Cybereason Japan株式会社(本社:Cybereason Inc.) |
Cybereason EDRは、世界的に有名なMITRE ATT&CK評価で上位スコアを記録する、ハイレベルな検知力を持つEDRです。
脅威を単なる「検出イベント」としてではなく、「攻撃全体のストーリー」として把握できる可視化力が最大の特長です。マルウェア感染だけでなく、内部侵入や横展開、認証情報の窃取など、攻撃者の行動を時系列で追跡できます。
さらに、AIによる行動分析エンジンがバックグラウンドで動作し、ゼロデイ攻撃やファイルレス攻撃など、従来のウイルス対策では検知が難しい脅威も正確に検出。加えて、国内拠点の「Cybereason Japan SOC」による24時間の監視体制と日本語サポートにより、グローバル製品ながら日本企業にも導入しやすい体制を整えています。
導入支援から運用監視、脅威分析までを一貫して提供するため、自社でSOCを構築するリソースがない中堅・中小企業でも安心して利用可能。スピード感のある攻撃にも柔軟に対応できる、実践的なEDRの代表格です。
Trend Vision One Endpoint Security

| 主な特徴 | AIを活用した脅威検知とEDR機能を統合し、高度な分析と自動対応を実現。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型(SaaS/オンプレミス併用可) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Android / iOS |
| 導入規模 | 中堅企業〜大企業(多拠点・クラウド環境に対応) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(年間サブスクリプション制) |
| 連携機能 | Trend Vision One XDR/Eメール・クラウド・ネットワークセキュリティ製品との連携 |
| サポート体制 | 24時間グローバルサポート、日本語サポートあり |
| 無料トライアル | あり(SaaS版で30日間) |
| 提供企業 | トレンドマイクロ株式会社(Trend Micro Inc.) |
「Trend Vision One Endpoint Security」は、トレンドマイクロが展開する次世代のエンドポイント防御ソリューションで、NGAV(次世代アンチウイルス)とEDR(エンドポイント検知・対応)を統合した設計を特徴としています。
単に既知のマルウェアを検出するだけにとどまらず、ファイルレス攻撃やランサムウェアの脅威にも対応可能となっています。特に注目すべきは、同社の拡張検知・対応プラットフォーム「Trend Vision One」との連携により、エンドポイントだけでなくメール、クラウド、ネットワーク、IDといった複数領域のテレメトリを相関分析できる点です。
これにより、単一デバイスの異常では捉えられない脅威の全体像を早期に把握し、影響を受けるシステムを迅速に隔離・修復に導く運用が可能となります。SaaS型で提供されることから、最新の脅威インテリジェンスが自動的に反映され、導入・運用面でもスムーズにモダンなセキュリティ体制へ移行できる点が大きな魅力です。
Cisco Secure Endpoint
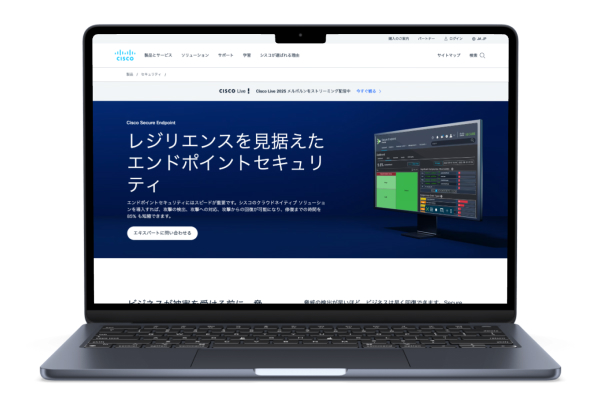
| 主な特徴 | ネットワーク・クラウド・エンドポイントを統合監視。XDR機能「Cisco SecureX」と連携。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型(Cisco Secure Cloud) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Android / iOS |
| 導入規模 | 中堅企業〜大企業(ネットワーク統合運用を重視する組織) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(年間サブスクリプション制) |
| 連携機能 | SecureX / Umbrella / Duo / Meraki などのCisco製品群と連携 |
| サポート体制 | 24時間グローバルサポート、日本語対応あり |
| 無料トライアル | あり(30日間) |
| 提供企業 | Cisco Systems, Inc. |
Cisco Secure Endpointは、世界最大級のセキュリティ企業であるCiscoが提供するEDR製品で、ネットワーク・メール・クラウドなど多層的な防御を統合できる点が特長です。
Cisco独自の脅威インテリジェンス「Talos」を活用し、最新の攻撃情報を自動反映することで、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃にも迅速に対応します。クラウドベースの管理コンソールにより、大規模環境でもリアルタイムで端末状況を監視可能。さらに、他のCisco製品群(SecureXやUmbrellaなど)と連携させることで、EDRを超えた拡張検知・対応(XDR)を実現します。
運用の可視化・自動化も進んでおり、SOC担当者の負担軽減にも貢献。グローバル展開する企業や、ネットワークとエンドポイントを統合的に守りたい企業に最適な製品です。
Symantec Endpoint Security Complete
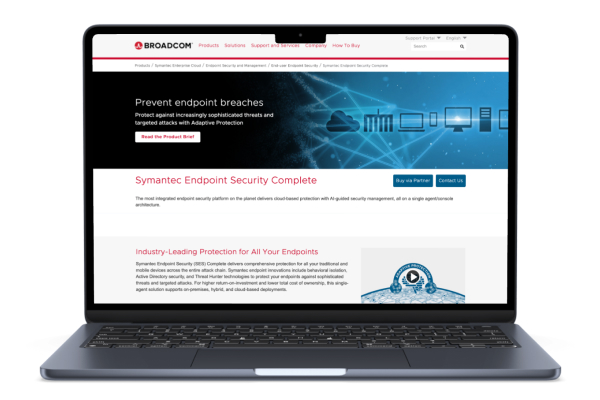
| 主な特徴 | アンチウイルス・EDR・デバイス制御を統合。AI分析と脅威インテリジェンスを活用。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型 / オンプレミス型 |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Android / iOS |
| 導入規模 | 中堅〜大企業(多拠点・金融・製造業での実績豊富) |
| 料金目安 | 要問い合わせ(年間契約制) |
| 連携機能 | Symantec Security Cloud / CASB / DLP / SIEM 連携可 |
| サポート体制 | 日本語サポート、24/7対応、Broadcomサポートポータル利用可 |
| 無料トライアル | あり |
| 提供企業 | Broadcom Inc.(旧Symantec) |
Symantec Endpoint Security Completeは、Broadcom傘下のSymantecが提供するエンタープライズ向け統合EDRです。
ウイルス対策・EDR・脅威ハンティングを一体化し、AIによる自動検知と修復機能を備えています。クラウドとオンプレミスをシームレスに統合管理できるため、複数拠点やリモート環境にも対応可能。特に金融・製造・官公庁など、情報保護レベルの高い業界での導入実績が多く、国際的なセキュリティ基準にも準拠しています。
自動修復・隔離機能により被害拡大を防ぎ、セキュリティ運用の効率化にも貢献。さらに、脅威インテリジェンス分析による予測的防御も強化されており、企業のリスクを未然に抑えます。堅牢性と安定性を重視する大企業にふさわしいハイエンド製品です。
ESET PROTECT MDR

| 主な特徴 | 軽量設計と高検知率が特徴。EPP+EDR+マネージド監視を一体化。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型 / オンプレミス型 |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Android |
| 導入規模 | 中小企業〜教育機関・官公庁 |
| 料金目安 | 月額数百円〜(端末単位課金) |
| 連携機能 | ESET LiveGrid / SIEM連携 / XDR拡張対応 |
| サポート体制 | 日本語サポート、メール・電話対応、MDR運用付きプランあり |
| 無料トライアル | あり(30日間) |
| 提供企業 | キヤノンマーケティングジャパン株式会社(ESET社製品) |
ESET PROTECT MDRは、ESET社の軽快な動作で知られるEDRに、24時間365日の監視と専門家対応を組み合わせたマネージド型EDRサービスです。
AIとヒューリスティック技術によって、未知の脅威やファイルレス攻撃を高精度で検知。自動隔離・調査レポート機能により、セキュリティ専門人材が不足する企業でも運用を継続できます。ESET製品の強みである「軽さ」はそのままに、MDR(Managed Detection and Response)体制によって、外部のセキュリティチームが分析・対応までをサポート。コストを抑えながら専門的な防御体制を構築できる点が評価されています。
中小企業から中堅規模の企業まで、リソース不足を補いながら堅実な防御を求める組織に適した選択肢です。
Sophos Intercept X Endpoint
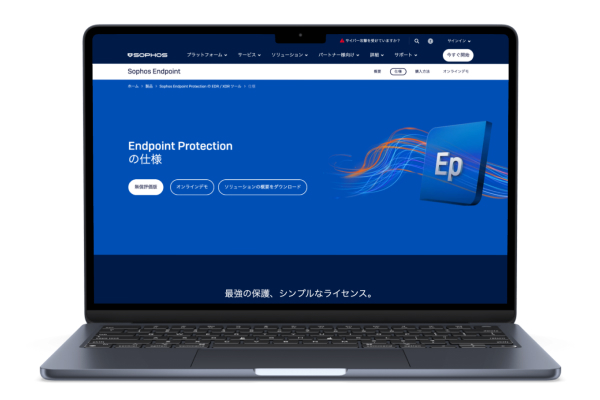
| 主な特徴 | AIディープラーニングによる未知の脅威検知。EDR/XDR機能を統合。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型(Sophos Central) |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux / Android |
| 導入規模 | 中小〜中堅企業(運用負荷軽減を重視する組織に最適) |
| 料金目安 | 月額数百円〜(端末単位、機能追加により変動) |
| 連携機能 | XDR / MDR(Sophos Managed Threat Response)連携可 |
| サポート体制 | 日本語サポート、24時間対応、グローバルSOCによる監視 |
| 無料トライアル | あり(30日間) |
| 提供企業 | Sophos Ltd. |
Sophos Intercept X Endpointは、ディープラーニングAIによって既知・未知の脅威を自動で検知・遮断する高精度なEDR製品です。
ランサムウェア、エクスプロイト、ファイルレス攻撃など多様な脅威をリアルタイムで防御し、攻撃の「発生から封じ込め」までを一気通貫で行います。Sophos Centralと呼ばれるクラウド管理コンソールにより、ファイアウォール・メールセキュリティ・モバイル管理など他製品と統合可能。XDRとしても機能し、企業全体の脅威情報を横断的に可視化できます。
また、直感的なインターフェースと自動隔離・修復の仕組みにより、専門知識がなくても運用しやすい点が魅力。世界中の中堅企業で導入実績があり、「運用のしやすさ」「安定性」「コストバランス」に優れた万能型EDRです。
KeepEye

| 主な特徴 | 国内企業向けMDRサービス。24時間監視と専門アナリストによる対応支援。 |
|---|---|
| 提供形態 | クラウド型 / マネージドサービス型 |
| 対応OS | Windows / macOS / Linux |
| 導入規模 | 中小企業〜中堅企業(セキュリティ人材不足対策に最適) |
| 料金目安 | 月額数万円〜(監視対象端末数による) |
| 連携機能 | 国内SOC連携、EDRベースのアラート監視 |
| サポート体制 | 日本語対応、国内SOCチームが運用代行 |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
| 提供企業 | S&J株式会社 |
KeepEyeは、S&J株式会社が提供する国産クラウド型EDRで、特に中小企業のセキュリティ強化を支援する目的で設計されています。
複雑な設定を必要とせず、導入後すぐにクラウド上から端末の監視・隔離・レポートを実行可能。国内サイバーセキュリティ専門家チームによる監視体制が整っており、攻撃検知から初動対応までを迅速に行います。国産ならではの日本語UIとサポート体制が充実しており、専門人材がいない企業でも安心して導入できるのが最大の特徴です。
また、コスト面でも導入しやすく、低価格帯ながらEDRの基本機能(検知・分析・対応)をすべて搭載。クラウド利用やリモートワークが進む中小企業に最適な、運用負荷の軽い実用型EDRです。
FFRI yarai

| 主な特徴 | 国産ヒューリスティック検知型EDR/EPP。未知の攻撃検知に強い。 |
|---|---|
| 提供形態 | オンプレミス型(スタンドアロン / オフライン環境対応) |
| 対応OS | Windows |
| 導入規模 | 官公庁・防衛・重要インフラ・製造業など |
| 料金目安 | 要問い合わせ(年間ライセンス制) |
| 連携機能 | SIEM連携、API提供あり |
| サポート体制 | 日本語サポート、専用保守窓口あり |
| 無料トライアル | あり(評価版提供) |
| 提供企業 | 株式会社FFRIセキュリティ |
FFRI yaraiは、株式会社FFRIセキュリティが開発した国産エンドポイント防御ソリューションで、国内官公庁・自治体・金融機関などでも採用される信頼性の高い製品です。
従来のシグネチャ方式に頼らず、「振る舞い検知」と「多層防御エンジン」により、未知のマルウェアや標的型攻撃を高精度で検出。インターネット接続のない閉域環境でも動作するため、機密性の高い業務環境にも適しています。シンプルな設計ながら、防御層ごとに異なる検知ロジックを組み合わせることで、多様な攻撃ベクトルに対応。国内サポートによる迅速なアップデート提供や、導入支援も充実しています。
クラウドに依存せず堅牢なセキュリティを構築したい企業に最適な、純国産EDR製品です。
HP Wolf Pro Security

| 主な特徴 | ハードウェアレベルの隔離機能で脅威を防御。AI行動分析と仮想化技術を組み合わせた独自設計。 |
|---|---|
| 提供形態 | プリインストール型(HP製端末向けクラウド連携サービス) |
| 対応OS | Windows(HP端末に最適化) |
| 導入規模 | 中小〜中堅企業、テレワーク利用環境に適用 |
| 料金目安 | 端末込みパッケージ価格(要問い合わせ) |
| 連携機能 | HP Wolf Security for Business との統合運用 |
| サポート体制 | 日本語サポート、HP Care Pack対応 |
| 無料トライアル | 要問い合わせ |
| 提供企業 | HP Inc. |
HP Wolf Pro Securityは、HPが提供するエンドポイント防御ソリューションで、同社製PCに標準搭載されている点が特徴です。
最大の強みは、ハードウェアレベルでの隔離と仮想化技術を組み合わせた多層防御。たとえば、添付ファイルやWebサイトを開く際に「仮想コンテナ」上で動作させることで、仮に悪意あるスクリプトが実行されても、実際のシステムには影響を与えません。これにより、未知のマルウェアやゼロデイ攻撃にも強い耐性を持ちます。
また、クラウド接続を必要とせずローカルで動作するため、オフライン環境や厳格な情報管理下でも運用可能。専任のセキュリティ人材がいない企業でも簡単に管理できる点が高く評価されています。PC端末そのものの防御力を高める仕組みとして、リモートワークやBYOD環境にも適しており、中小企業や自治体、教育機関での導入も増加中。軽量・低コストながら堅牢なセキュリティを実現できる実用的なEDR製品です。
EDRの導入に関するよくある質問に回答
EDRは高機能なセキュリティ製品である一方、価格や導入期間、運用方法などが分かりづらいという声も多く聞かれます。
ここでは、初めて導入を検討する企業が特に疑問を感じやすいポイントを中心に、基本的なQ&A形式で解説します。費用感や導入スケジュール、クラウド型とオンプレミス型の違いなど、実際の検討に役立つ要素をわかりやすく整理しました。
自社の規模やセキュリティ体制に合わせて最適な選択ができるよう、判断の目安として活用してください。
EDRの導入にはどれくらい時間がかかりますか?
EDRの導入期間は、企業規模や環境によって異なりますが、中小企業であれば1週間〜1か月程度が一般的な目安です。
クラウド型EDRであれば、管理画面からエージェントを配布するだけで導入でき、最短で数日以内に運用を開始できます。これに対してオンプレミス型は、サーバー構築やネットワーク調整が必要となるため、1〜2か月かかることもあります。
また、セキュリティポリシーの策定や運用ルールの整備を同時に行うことで、導入後のトラブルを防げます。特に大規模企業では、全端末への段階的な導入やトライアル(PoC)を経て本格運用するケースが多く、プロジェクトとして2〜3か月を見込むのが現実的です。
クラウド型とオンプレミス型はどちらを選ぶべき?
クラウド型とオンプレミス型には、それぞれ明確なメリットと課題があります。
クラウド型EDRは初期費用が少なく、導入・運用が簡単で、最新の脅威情報が自動で更新されるのが強みです。IT担当者が少ない中小企業やリモートワーク環境では特におすすめです。
一方、オンプレミス型EDRは自社サーバー上で運用するため、外部へのデータ送信を制限でき、機密情報を扱う金融・官公庁・防衛関連企業などで選ばれる傾向があります。ただし、導入・保守コストは高くなりがちです。
近年では両者の中間にあたる「ハイブリッド型」や、クラウドで集中管理しつつローカルで検知を行うモデルも増えています。選定時は「情報管理の厳格性」と「運用負荷」のバランスを基準に考えるとよいでしょう。
EDRを導入したら100%安全になりますか?
EDRを導入しても、残念ながら100%安全になるわけではありません。EDRは「侵入されることを前提に、早期に検知して被害を最小限に抑える」ことを目的とした対策です。つまり、攻撃そのものをすべて防ぐのではなく、「侵入後の動きを監視・分析し、被害を広げない」ことに強みがあります。
そのため、EPP(ウイルス対策ソフト)やファイアウォール、アクセス制御などの多層防御と組み合わせることが重要です。また、従業員のセキュリティ教育や運用ルールの整備も欠かせません。EDRは強力な防御手段の一つですが、最終的な安全性は「技術×人×運用」の総合力で決まります。
